角田光代さんエッセイ 暮らしのカケラ(19) 「世界をひとつ多く持つ」
 photo・T.Tetsuya
photo・T.Tetsuyaあたらしい何かをはじめることにかんして、私は腰が重いほうだ。ふだんはそんなことは考えもしないのだけれど、趣味の多い友人と話していると、そう思い知らされる。趣味の多い人というのは、信じられないくらい軽やかに、あたらしい世界に足を踏み入れる。
あたらしいことといってもいろいろある。パン作りや刺繍ならばひとりでもはじめられるが、茶道や豆本作りや楽器演奏などとなると、どこかに習いにいったほうがてっとり早い。
ひとりでできることならば私も挑戦することはあるが、習いにいくとなると、まず躊躇する。年若いころだったら、この躊躇も度合いが軽かった。二十代の私は着付け教室に通ったし、三十代の私はボクシングジムに入会した。しかしながら四十歳を過ぎると、あたらしい場所は敷居が高くなる。しかも、年齢を重ねると、あたらしくはじめたい多くのことが実生活にはさほど役立たないとわかってしまう。ギターを弾けるようになったからといって、それで食べられるはずもない、発表会に出るのがせいぜいだろうと、夢のないことを考えてしまう。
趣味の多い人たちを見ていると、年齢にも、役立つか否かにも関係なく、おもしろそうだと思ったらすぐに動き出している。知らない人たちのなかにも平気で交じりにいく。同世代の友人たちが、急に草木染めをはじめたり、ゴスペルをはじめたり、合気道をはじめたりするのを、私はいつも驚きとうらやましさのまじった気持ちで見たり聞いたりしている。
腰が重いのに、いや、腰が重いからこそなのかもしれないが、私は習いごと関係の案内を見るのが好きだ。たとえば新聞に折り込まれているカルチャーセンターのチラシや区の広報誌など。ウクレレとかワイン入門とか、仏像の魅力とか古墳の旅とか、講座紹介を読むだけでわくわくする。まさに、今まで閉じていた扉がどんどん開いていく気分になる。でも、じゃあ申しこんでみよう、見学にいってみようと、行動に移すことができない。
先だって、あるカルチャーセンターに呼ばれて、友人と公開対談をした。対談前、広いセンター内の廊下を歩いていたら、コロナ感染対策のためだろう、どの教室もドアが開け放たれ、レッスンの様子が見えた。子どもたちのバレエレッスンや、語学の授業が見えた。ある教室で、先生と向き合って生徒さんがひとり、タップダンスを踊っていた。時節柄、ほかの生徒さんはお休みなのか、それとももともと受講生がひとりなのか。生徒さんのダンスはけっしてうまくはないのだけれど、かっこよかった。ずっと見ていたかった。実生活に役立つかそうでないかなんて関係なく、世界をひとつ多く持つっていいなと、あらためて思ったのだった。
プロフィール
かくた・みつよ
作家。1967年、神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。1990年「幸福な遊戯」で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。『対岸の彼女』(文藝春秋)での直木賞をはじめ著書・受賞多数。最新刊は『銀の夜』(光文社)。
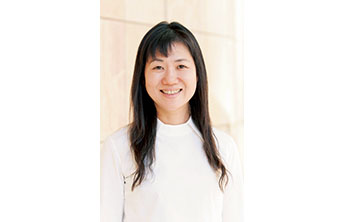
角田光代さんエッセイ バックナンバー
UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]
UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。
冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。


![URPRESS 2022 vol.68 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress68/hndcds0000001meh-img/68_common_header.png)