角田光代さんエッセイ 暮らしのカケラ(18) 「ものに心を分ける」
 photo・T.Tetsuya
photo・T.Tetsuyaなつかしいという気持ちは、年を重ねるごとにどんどん増える。ラジオから昔の歌謡曲が流れてくればなつかしくなり、学生時代の同級生に会えばなつかしいと連発し、かつて住んでいた町を歩くと猛烈ななつかしさがこみあげてくる。過去が増えていくのだから、あたりまえのことだ。
最近になって、意外なものになつかしさを感じている自分に気づき、ちょっと驚いた。意外なもの──それは服である。着物や、とくべつな意味がある衣類以外、たいていの服は手放して暮らしてきた。二十代のころに着ていた服なんて一枚も残っていない。三十代のころのものは、スーツやコートにかぎって、かろうじて数着ある。その何十倍、いや何百倍もの服を、処分したり寄付したり、なくしたりしてきた。ごくあたりまえのことだと思う。
三十代のころの写真がたまたま出てきたりすると、そこに写っている自分より友だちより背景より、自分の着ている服に目がいく。ああ、あったなこんな服、と思うやいなや、その服にかんする記憶がはらはらとあふれ出てくる。それを見つけた店、買いたいと思った気持ち、店員さんとのやりとり、その服を着ていった会合、合わせたほかの服や靴。猛烈ななつかしさがこみあげる。
もちろんすべての服にたいして、そんなふうに思い出をあふれさせているわけではない。ごく一部の服にかんして、出合いの場所や着ていた時期を鮮明に覚えている。それを手放す決心をしたときのことも覚えていて──子どもっぽい、似合わなくなった、変色した、二年以上着なかった等々──、案外未練なく処分している。けれどなつかしさでいっぱいになったときには、なぜ手放したんだろうと後悔に似た気持ちを味わう。その服が手元にあったとしても、着ないのはわかっているが、でも、見たい。触れたい。いや、愛でたい、というのが、いちばん近い表現かもしれない。
そう思ってみると、服は私にとって、たんなる実用品でも消耗品でもないのだとあらためて気づく。私はおしゃれにも着心地にも流行にも興味がなく、気に入りの文房具や食器のように、好きな意匠の服がただただ好きなのである。色が好き、デザインが好き、というほかに、胸元の(一センチ四方ほどの)刺繍が好きだとか、背後のリボンが好きだとか、袖のボタンが好きだとか、ときにはプリントの馬鹿馬鹿しさがいいという理由が、購入の決め手となる。だから、買ったときのことを鮮明に覚えているのだ。私にとって服は、一定の期間にせよ、心を分けた何かであるらしい。
今手元にある服を、着なくなったからといって今後は処分せず、愛でるためだけにずっととっておく、なんてことは不可能だ。けれども、服にたいするなつかしさを自覚して以降、服の処分には以前よりずっと慎重になった。断捨離という概念は、私の暮らしには不向きなようだ。
プロフィール
かくた・みつよ
作家。1967年、神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。1990年「幸福な遊戯」で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。『対岸の彼女』(文藝春秋)での直木賞をはじめ著書・受賞多数。最新刊は『銀の夜』(光文社)。
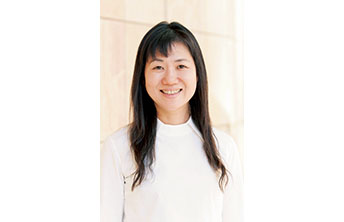
- LINEで送る(別ウィンドウで開きます)
角田光代さんエッセイ バックナンバー
UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]
UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。
冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。


![URPRESS 2021 vol.67 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress67/lrmhph000001z7gh-img/67_common_header.png)