【特集】URの経験と知見を能登半島の復旧・復興へ
今年の元日に発生した令和6年能登半島地震。 URは国からの要請を受け、いち早く職員を現地に派遣。 他の自治体からの応援スタッフとともに、これまでの経験を生かして復旧・復興の手伝いに汗を流している。
仮設住宅建設を後方から支える
これまでも地元自治体とともに、東日本大震災などの大規模災害からの復旧・復興のお手伝いをしてきたUR。今回の能登半島地震では、まず住家の被害認定業務支援、応急仮設住宅の建設支援、被災宅地危険度判定広域支援に職員を派遣した。
応急仮設住宅建設支援の第一陣として、URの花房龍宗(りょうそう)が石川県に派遣されたのは1月15日。東日本大震災で被災した福島県、宮城県、岩手県と、熊本地震で被災した熊本県から派遣された職員、それに現場の施工業者とともに、まず被災した輪島市、珠洲(すず)市などの4市4町の仮設住宅用の土地を確認しに行った。厳しい道路事情のため、ベースのある金沢市から現地まで、車で片道4~5時間かかったという。
「行ってみると、地割れが起きていたり、危険な崖の近くだったりと、仮設住宅には向かない場所もありました。問題のない場所であれば、市町に伝え、建設が動き出します」
地元自治体の担当者らは、目の前の課題への対応で手いっぱい。まして仮設住宅づくりははじめてだ。ここでは被災地で仮設住宅をつくってきたURや被災県の職員たちの経験が生きた。
「まず、仮設住宅の基準を決める班と、仕事の進め方を決める班の2つに分かれ、それぞれを固めていきました。これが決まれば、応援職員が交代しても、スムーズに仕事が進められます。また、被災した県の職員からは、畑地や公園用地などを仮設住宅用に借りる場合、後で土地を戻すときの条件について話しておかないと、トラブルになるといった、経験した者ならではのアドバイスもあり、これらも業務フローに落とし込みました」(花房)
施工業者が夜遅く打ち合わせに訪れることも多く、誰もが1日も早い仮設住宅完成に最大限の努力を続けていた。
「URには仮設住宅建設を経験した者が残した資料があり、私も事前にそこから情報を得ることで、速やかに業務を進めることができました。これまでの経験がつながったと感じています」と花房は振り返る。
 輪島市に完成したプレハブ式の応急仮設住宅。
輪島市に完成したプレハブ式の応急仮設住宅。 珠洲市に完成したプレハブ式の応急仮設住宅。下水道の復旧が難航しているのが課題だ。
珠洲市に完成したプレハブ式の応急仮設住宅。下水道の復旧が難航しているのが課題だ。 「自分がいる間に仮設住宅の完成を見ることはできなかったが、初期段階の基礎固めができた」と話す花房。
「自分がいる間に仮設住宅の完成を見ることはできなかったが、初期段階の基礎固めができた」と話す花房。危険度判定作業をマネジメントする
被災宅地危険度判定広域支援に派遣されたのは末松孝朗。2月12日から要請のあった内灘(うちなだ)町、羽咋(はくい)市、宝達志水(ほうだつしみず)町で、宅地の危険度判定をマネジメントする業務を行った。宅地危険度判定というのは、危険度を赤、黄、青で示し二次災害を防ぐ大切な作業。
「この1市2町に、危険度判定を行うチームが全部で38班入っています。私の仕事は判定活動全体の運営で、進捗管理や作業割振りなどの後方支援です」
特に末松が担当した内灘町は、震度こそ5弱だが、砂丘状の軟弱な地盤のため液状化と側方流動(そくほうりゅうどう)が起こり、かなり危険な状態になっていた。
「住宅の倒壊はなくても、地盤が横に大きくずれている所もあり、今後、どのように復旧・復興させるのか、大いに検討する必要がありました」と末松は言う。
「被災地支援は初めての経験でしたが、先輩が行ってきたことを見聞きしていたので、スムーズに取り組むことができたと思います」
 各戸を回り、宅地の危険度を調べてその結果を赤、黄、青で示して住宅や外壁に貼りだす被災宅地危険度判定。URはこの作業のマネジメントなどを行った。
各戸を回り、宅地の危険度を調べてその結果を赤、黄、青で示して住宅や外壁に貼りだす被災宅地危険度判定。URはこの作業のマネジメントなどを行った。 焼失した輪島市内の朝市通り。
焼失した輪島市内の朝市通り。 輪島市の朝市通りは大火に見舞われた。被害の様子を記録するUR職員。
輪島市の朝市通りは大火に見舞われた。被害の様子を記録するUR職員。 末松は「内容こそ違えど、行政の人たちと一緒に進める仕事は普段と同じ」と振り返った。
末松は「内容こそ違えど、行政の人たちと一緒に進める仕事は普段と同じ」と振り返った。復興まちづくりに経験を生かして
「大規模災害後、自治体は復旧作業と同時に、復興計画づくりを進める必要がありますが、現地はまだ復旧作業で手一杯で、自治体によって被害の状況も異なります。被災した自治体が復興計画づくりをスタートさせた際に、東日本大震災などの経験をもつURが、そのときの知見を復興まちづくりに生かせると考えています」
こう話すのは松村秀弦(ほづる)。国土交通省に同行して現地に赴き、自治体のニーズを聞き取るチームの指揮をとっている。
「能登半島地震では、生業(なりわい)と生活基盤の復興、インフラの強靭化が大事になってくると思います」と話すのは、東日本大震災のときにも復興支援に従事した橋本大和(ひろかず)だ。
東京の木造家屋が密集している地域や糸魚川大火の復興での土地の再編手法が、今回の復興に生かせるのではと考えているという。
「被害に遭ったまちを、よりよいまちにすることが私たちの使命。市や町に寄り添いながら、URのノウハウを活用したい」(松村)
能登半島の一日も早い復興のために、URスタッフの気持ちは一つになっている。
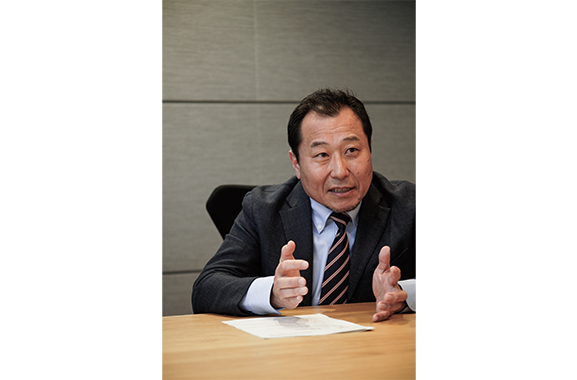 東日本大震災でも発災後、第一陣として現地調査に入った橋本。東北で培った経験を能登半島に生かす。
東日本大震災でも発災後、第一陣として現地調査に入った橋本。東北で培った経験を能登半島に生かす。 これまでのURの経験を生かし、自治体に適切なアドバイスをしていきたいと話す松村。
これまでのURの経験を生かし、自治体に適切なアドバイスをしていきたいと話す松村。【武田ちよこ=文、菅野健児=撮影(人物)】
- Xポスト(別ウィンドウで開きます)
- LINEで送る(別ウィンドウで開きます)
特集バックナンバー
UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]
UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。
冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。


![URPRESS 2024 vol.77 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress77/ip8i2r0000001lom-img/header_77.png)






