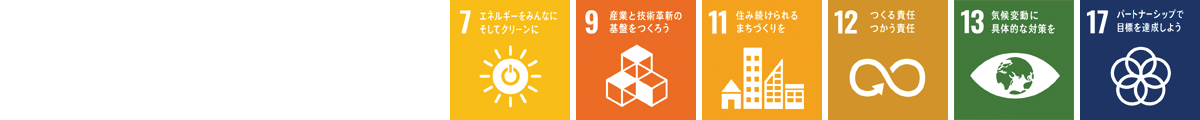【特集】防災でまちづくりを! 「ぼうさい夏市」で地域がつながる 弥生町三丁目周辺地区(東京都中野区)
避難道路や防災公園の整備を通して、安全・安心で、住みたくなるまちづくりを続けてきた弥生町三丁目周辺地区。この夏、防災に特化した初めてのイベントが開催された。
ぼうさい夏市で多彩な防災体験
 起震車や煙幕ハウス(煙体験)などで災害時の様子を体験できる、ぼうさい夏市。
起震車や煙幕ハウス(煙体験)などで災害時の様子を体験できる、ぼうさい夏市。
 子どもに人気があったのは、消火器噴射体験。
子どもに人気があったのは、消火器噴射体験。 消防車の乗車体験も話題に。運転席はたくさんの装備で囲まれていた。
消防車の乗車体験も話題に。運転席はたくさんの装備で囲まれていた。8月最後の週末(26・27日)、中野区の川島公園で「ぼうさい夏市」と題したイベントが開かれた。
メイン会場の川島公園は、中野区が取り組む弥生町三丁目周辺地区の防災まちづくりで整備された、防災機能をもつ公園だ。災害時の利用も考慮して、防災井戸やマンホールトイレ、パーゴラテントなどが整備されている。それら設備の使い方実演をはじめ、起震車や煙幕ハウス、消火器噴射体験やテントでのダンボールベッドづくり、さらには消防車の乗車体験も話題に。防災に関わる多彩な企画が用意された「ぼうさい夏市」。子ども連れのファミリーなど地域の人々が集まり、ふだんはできない体験を楽しんでいた。
不燃領域率は50%から70%に
「昭和の匂いがする、昔ながらの商店街が残る地域なんですよ」
弥生町三丁目についてそう説明するのは、地元の川島商店街振興組合理事長の坂入勝美さんだ。青果店「坂入商店」を営む坂入さんの言葉どおり、新宿に近い都心でありながら懐かしい雰囲気が残る弥生町三丁目地区。一方で、道幅の狭い道路や行き止まりが多く、「避難用の道路ネットワークの整備」や「消防車が入れる幅員6メートルの避難路の確保」「沿道の建物の不燃化促進」などが課題となっていた。
中野区の要請を受けたURは、2016(平成28)年から都営川島町アパート跡地の土地区画整理事業に着手。避難道路や防災機能をもった公園、密集事業の事業協力者の移転先として従前居住者用賃貸住宅「コンフォール中野新橋」を整備するなど、区と共に防災性の向上と居住環境の改善を進めてきた。
川島公園と「コンフォール中野新橋」が完成した19年にまちびらきが行われたものの、その後、コロナ禍となり地域の活動がストップ。ぼうさい夏市が、久しぶりに人々が集うイベントとなった。
中野区まちづくり事業課の楠居雅伸さんは、イベントの調整に当たるなかで、地域の方々が汗を流して準備される姿や、会場で久しぶりに会った方たちがうれしそうに会話するのを見て、地域の方の期待、そして今回のようなイベントの必要性を実感したという。
「公園や道路の整備を第1期としたら、このイベントを機に地域に目を向けてもらうことで第2期に進みました。引き続き取り組みの支援に努めていきます」と話す。
日頃、公園内の防災倉庫を管理しているのは、弥生町三丁目町会防災部。防災部の前部長である遠藤文夫さんは、整備による地域の環境変化を実感しているという。弥生町三丁目周辺地域の火災の際の燃え広がりにくさを示す不燃領域率は50%から70%近くにまで改善されている。
「この公園は災害時に一時避難できる場所の役目もあります。防災のイベントを行うのは初めてですが、これを機に防災訓練を定期的に開催していきたいですね」と遠藤さん。
 川島商店街振興組合の坂入さん。組合では、イベント後の夕方に「川島夜店市」を開催した。
川島商店街振興組合の坂入さん。組合では、イベント後の夕方に「川島夜店市」を開催した。 この日、対面でのイベントの意義を改めて感じたと話す中野区の楠居さん。
この日、対面でのイベントの意義を改めて感じたと話す中野区の楠居さん。 工学院大学の学生によるテント体験コーナー。
工学院大学の学生によるテント体験コーナー。 ダンボールベッドの性能に驚く声が多かった。
ダンボールベッドの性能に驚く声が多かった。 町会防災部メンバーが園内の設備の使い方を実演。
町会防災部メンバーが園内の設備の使い方を実演。 井戸水は、マンホールトイレの貯水槽へ流すことができる。
井戸水は、マンホールトイレの貯水槽へ流すことができる。 パーゴラ(日陰棚)のテントは平時はベンチの中に収納されている。
パーゴラ(日陰棚)のテントは平時はベンチの中に収納されている。 防災倉庫から備品を取り出す町会防災部の遠藤さん。
防災倉庫から備品を取り出す町会防災部の遠藤さん。安全・安心で住みたくなるまちに
画期的なのは、ぼうさい夏市が多岐にわたる団体の協力のもとで開催されたことだ。主催は工学院大学、川島商店街振興組合、UR。そして中野区、弥生町三丁目町会防災部、中野消防団第一分団が共催している。
この地域でフィールドワークを行っている工学院大学建築学部まちづくり学科の野澤研究室。そのメンバーのひとり、大学4年の髙橋颯太さんは、ぼうさい夏市の準備を通して、日頃は交流のない世代、60代、70代の方と交流できたのがよかったという。イベントでは子ども向けのスーパーボールすくいや避難時を想定してのテント体験などを学生たちで用意した。
イベントの実現に向けて奔走し、関連団体との調整を重ねてきたのはURの岡田一志。入社1年目のホープだ。
「関東大震災から100年をきっかけに地域の方に防災設備を知ってもらい、地域の防災について考えるきっかけになればとの思いで準備してきました。安全・安心なまちづくりを通して、地域全体の活力向上につなげていけたらと思っています」
イベント会場では来訪者と運営者を対象にしたアンケートを実施。その結果を今後の持続的な防災まちづくりの参考にしていく。目指すのは、地域の活性化であり、安全・安心な住みたくなるまちづくりだ。
 来場者へアンケートを依頼するURの岡田(右)。テントの設置や飲み物の配布など暑さ対策にも配慮した。
来場者へアンケートを依頼するURの岡田(右)。テントの設置や飲み物の配布など暑さ対策にも配慮した。
【妹尾和子=文、菅野健児=撮影】
【特集】高規格堤防を整備して魅力あるまちが生まれた 大和川左岸(三宝 さんぼう)土地区画整理事業(大阪府堺市)
 古くから氾濫を繰り返してきた一級河川大和(やまと)川。その河口に近い堺市の三宝地区で、高規格堤防整備と一体化した安全安心なまちづくりが進んでいる。
古くから氾濫を繰り返してきた一級河川大和(やまと)川。その河口に近い堺市の三宝地区で、高規格堤防整備と一体化した安全安心なまちづくりが進んでいる。【特集】防災でまちづくりを!「ぼうさい夏市」で地域がつながる 弥生町三丁目周辺地区(東京都中野区)
 避難道路や防災公園の整備を通して、安全・安心で、住みたくなるまちづくりを続けてきた弥生町三丁目周辺地区。この夏、防災に特化した初めてのイベントが開催された。
避難道路や防災公園の整備を通して、安全・安心で、住みたくなるまちづくりを続けてきた弥生町三丁目周辺地区。この夏、防災に特化した初めてのイベントが開催された。【特集】大切なのは、日頃からの「助け」を求め合える関係づくり 花畑(はなはた)団地(東京都足立区)
 今年度、管理開始から60周年を迎える花畑団地では、昨年から地区防災計画づくりが進められてきた。それは、いざというときに支え合える関係づくりでもある。
今年度、管理開始から60周年を迎える花畑団地では、昨年から地区防災計画づくりが進められてきた。それは、いざというときに支え合える関係づくりでもある。【特集】密集市街地の課題を解消し「燃えない・燃え広がらないまち」へ 豊町・二葉・西大井地区(東京都品川区)
 地震による火災危険度などが高かった密集市街地で始まった、防災まちづくり。事業に協力する住民のための賃貸住宅や防災広場など、安全・安心なまちづくりへの取り組みが進行中だ。
地震による火災危険度などが高かった密集市街地で始まった、防災まちづくり。事業に協力する住民のための賃貸住宅や防災広場など、安全・安心なまちづくりへの取り組みが進行中だ。【特集】「密集市街地整備と自然災害への備え」をテーマに、URがセッションを開催 ぼうさいこくたい2023
 9月17、18日、横浜市の横浜国立大学を会場にして、「ぼうさいこくたい2023」が開催された。URはこれまで取り組んできた密集市街地整備をテーマに、関係者とのセッションを行った。
9月17、18日、横浜市の横浜国立大学を会場にして、「ぼうさいこくたい2023」が開催された。URはこれまで取り組んできた密集市街地整備をテーマに、関係者とのセッションを行った。特集バックナンバー
UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]
UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。
冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。


![URPRESS 2023 vol.75 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress75/v8klms0000003676-img/header_75.png)