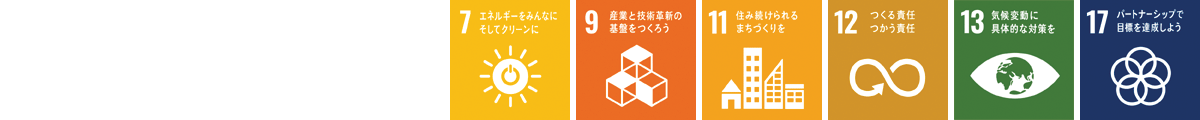【特集】高規格堤防を整備して魅力あるまちが生まれた 大和川左岸(三宝 さんぼう)土地区画整理事業(大阪府堺市)
古くから氾濫を繰り返してきた一級河川大和(やまと)川。その河口に近い堺市の三宝地区で、高規格堤防整備と一体化した安全安心なまちづくりが進んでいる。
幅100メートルの堤防がまちを守る
大阪の三大夏祭りの一つ、住吉大社の住吉祭のクライマックスは、大神輿が大和川の中を練り歩く神輿渡御(みこしとぎょ)。この舞台となる大和川は、大阪市と堺市を隔てる一級河川で、奈良県北東部を源流に、大阪平野を西に進み大阪湾へと流れ込んでいる。
過去には氾濫を繰り返し、江戸時代に川の付け替えが行われたが、現在に至るまで下流は洪水の危険にさらされてきた。特に周辺は人口も多く、工場などもあるので、万一水害が発生した場合の被害は甚大なものになる。そこでこのエリアの安全を守り、よりよいまちにするため、下流域の左岸、堺市の三宝地区で、高規格堤防をつくる大規模なプロジェクトが進められている。
スーパー堤防とも呼ばれる高規格堤防とはどういうものか。国土交通省近畿地方整備局でこの事業を担当する大西洋平さんに伺った。
「想定以上の大雨による洪水が発生しても、堤防が削れたり、決壊することがないよう、幅を拡げた堤防のことを高規格堤防と呼びます。大和川では従来の堤防から市街地側に盛土して、堤防の幅を100メートル以上に拡げ、緩やかな台地状に整備します。これでたとえ越水することはあっても、堤防決壊によって市街地が壊滅的な被害を受けることが防げます」
 大和川左岸の先行整備街区には、住宅が建ち、公園も整備。新しいまちが生まれている。川をはさんで写真の左側は大阪市。
大和川左岸の先行整備街区には、住宅が建ち、公園も整備。新しいまちが生まれている。川をはさんで写真の左側は大阪市。 盛土した土地の川沿いの道は自動車進入禁止。川風を受けながらサイクリングやジョギング、ウォーキングが楽しめる。
盛土した土地の川沿いの道は自動車進入禁止。川風を受けながらサイクリングやジョギング、ウォーキングが楽しめる。 従来の堤防から市街地側に盛土して造った高規格堤防の上に、新しいまちが生まれている。
従来の堤防から市街地側に盛土して造った高規格堤防の上に、新しいまちが生まれている。 先行して整備された阪神高速大和川線。
先行して整備された阪神高速大和川線。同じエリアへの移転で交渉もスムーズに

この事業によって、従来の堤防から南側に約100メートル先まで続く新たな台地が、川沿いに生まれる。だが、そのためには、ここに住んでいた人たちに移転してもらわなければならない。地権者は約300人。移転に関する対応は堺市とURが行った。
「地権者様1軒1軒を訪ね、この事業の必要性を真摯にご説明してきました。これまでに約9割の地権者様から、移転にご協力いただくことができました」とURの林 陽平が説明する。
移転をスムーズに進めるために「一度移転」という方法も取り入れた。これは、今回の整備街区にある工場跡地などを先行整備街区として、高規格堤防の盛土と、土地区画整理事業による宅地整備を進め、ここに移転してもらう方法だ。住民からすれば一度の引っ越しで済み、しかも住み慣れた同じエリアで暮らせる。
「この地区は60代以上の高齢世帯が7割を超えており、地区外に引っ越して土地勘のないまちで新しい生活を始めるのは、ハードルが高いと感じる方が多かったです。でも、同じ地区内への引っ越しなら、生活を再建するイメージを持ちやすいのかなと思います。皆さん、この事業の大切さを理解してくださり、移転にご協力いただけたと感じています」
堺市都市整備部の今上(いまうえ)剛さんがこう振り返る。
先行整備街区を訪れると、真新しい住宅地が生まれ、人々の暮らしが始まっていた。エリア内には都市計画公園もあり、川沿いには自転車専用道も整備されている。
堺市は、100㎡未満の土地所有者で、地区外に移転を希望する方の土地を買い取ったり、また、公営住宅のあっせんなど、生活再建の手助けも行った。
 「高規格堤防の整備は、人々の暮らしを水害から守ります」と国交省の大西さん。
「高規格堤防の整備は、人々の暮らしを水害から守ります」と国交省の大西さん。 住み慣れたまちの中で、安心して新たな暮らしが始められる。
住み慣れたまちの中で、安心して新たな暮らしが始められる。 堺市の今上さんは「目の前に新しいまちができあがってくるのを見ると感慨深い」と話していた。
堺市の今上さんは「目の前に新しいまちができあがってくるのを見ると感慨深い」と話していた。4者が密接に関わる希少なプロジェクト
このプロジェクトの特徴はもうひとつある。事業者が4者あり、それぞれが密接に関わりながら、役割を分担して事業を円滑に進めている点だ。その4者とは堺市、国土交通省、阪神高速道路、それにUR。
国土交通省は盛土をして大和川高規格堤防を整備する。阪神高速道路は、その堤防の下に阪神高速大和川線を整備する。URは区画整理による円滑な移転により、高規格堤防の早期整備に貢献する。堺市はこれらの事業を一体的に進め、防災・減災力の向上に取り組んでいく。
阪神高速大和川線は、すでに全線開通しており、その上の土地は新しいまちに生まれ変わっている。堺市の今上さんは、「ここは堺市の玄関口。一体整備を進めることで、安全で安心して暮らしやすいまちが、さらに将来にわたって快適で魅力あふれる都市として発展してくれれば」と期待する。
「移転にご協力いただいている地権者様に宅地を期限通りお返しすることが、現時点の目標です。お戻りいただいた皆さまに、安心して暮らしていただけるまちづくりを目指します」とURの林がしめくくった。
 「新しいまちに道路ができて、津波避難所になっている阪神高速の換気所へのアクセスがよくなった」とURの林は防災面の向上にも言及。
「新しいまちに道路ができて、津波避難所になっている阪神高速の換気所へのアクセスがよくなった」とURの林は防災面の向上にも言及。
【武田ちよこ=文、菅野健児=撮影】
【特集】高規格堤防を整備して魅力あるまちが生まれた 大和川左岸(三宝 さんぼう)土地区画整理事業(大阪府堺市)
 古くから氾濫を繰り返してきた一級河川大和(やまと)川。その河口に近い堺市の三宝地区で、高規格堤防整備と一体化した安全安心なまちづくりが進んでいる。
古くから氾濫を繰り返してきた一級河川大和(やまと)川。その河口に近い堺市の三宝地区で、高規格堤防整備と一体化した安全安心なまちづくりが進んでいる。【特集】防災でまちづくりを!「ぼうさい夏市」で地域がつながる 弥生町三丁目周辺地区(東京都中野区)
 避難道路や防災公園の整備を通して、安全・安心で、住みたくなるまちづくりを続けてきた弥生町三丁目周辺地区。この夏、防災に特化した初めてのイベントが開催された。
避難道路や防災公園の整備を通して、安全・安心で、住みたくなるまちづくりを続けてきた弥生町三丁目周辺地区。この夏、防災に特化した初めてのイベントが開催された。【特集】大切なのは、日頃からの「助け」を求め合える関係づくり 花畑(はなはた)団地(東京都足立区)
 今年度、管理開始から60周年を迎える花畑団地では、昨年から地区防災計画づくりが進められてきた。それは、いざというときに支え合える関係づくりでもある。
今年度、管理開始から60周年を迎える花畑団地では、昨年から地区防災計画づくりが進められてきた。それは、いざというときに支え合える関係づくりでもある。【特集】密集市街地の課題を解消し「燃えない・燃え広がらないまち」へ 豊町・二葉・西大井地区(東京都品川区)
 地震による火災危険度などが高かった密集市街地で始まった、防災まちづくり。事業に協力する住民のための賃貸住宅や防災広場など、安全・安心なまちづくりへの取り組みが進行中だ。
地震による火災危険度などが高かった密集市街地で始まった、防災まちづくり。事業に協力する住民のための賃貸住宅や防災広場など、安全・安心なまちづくりへの取り組みが進行中だ。【特集】「密集市街地整備と自然災害への備え」をテーマに、URがセッションを開催 ぼうさいこくたい2023
 9月17、18日、横浜市の横浜国立大学を会場にして、「ぼうさいこくたい2023」が開催された。URはこれまで取り組んできた密集市街地整備をテーマに、関係者とのセッションを行った。
9月17、18日、横浜市の横浜国立大学を会場にして、「ぼうさいこくたい2023」が開催された。URはこれまで取り組んできた密集市街地整備をテーマに、関係者とのセッションを行った。特集バックナンバー
UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]
UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。
冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。


![URPRESS 2023 vol.75 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress75/v8klms00000035mj-img/header_75.png)