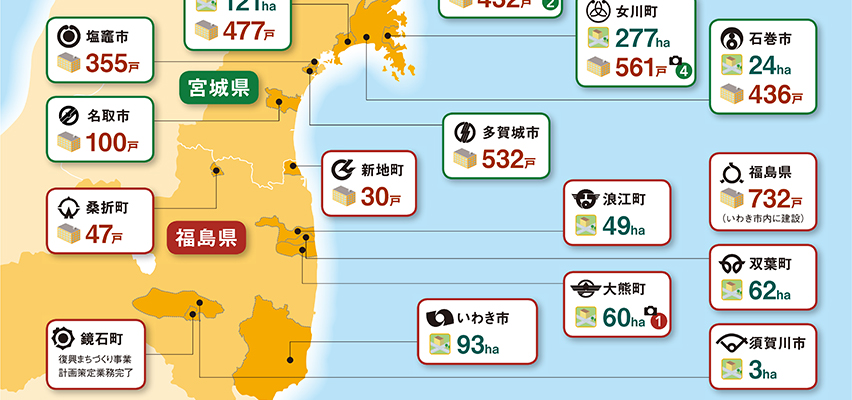【特集】岩手県陸前高田市
 かさ上げ地に商店や商業施設、公共施設が建つ高田地区。
かさ上げ地に商店や商業施設、公共施設が建つ高田地区。新たな挑戦に期待が膨らむ
生まれ変わったまち
白砂青松の景勝地「高田松原」を飲み込み陸前高田の市街地を襲った15mに及ぶ津波。
陸前高田市の被災面積は東北の被災3県でも最大だった。
甚大な被害を受けたまちが整備され、いま新たな息吹に包まれている。
 高田地区の商店街。今泉・高田地区ともに七夕のお祭りで巨大な山車が出るため、通常のアスファルトより強度を高めた。
高田地区の商店街。今泉・高田地区ともに七夕のお祭りで巨大な山車が出るため、通常のアスファルトより強度を高めた。 2014年、高田地区に先行して建てられた下和野災害公営住宅。現在、背後の山側に市役所を建設中。
2014年、高田地区に先行して建てられた下和野災害公営住宅。現在、背後の山側に市役所を建設中。 高田松原津波復興祈念公園内に建てられた「道の駅 高田松原」と東日本大震災津波伝承施設「いわてTSUNAMIメモリアル」。
高田松原津波復興祈念公園内に建てられた「道の駅 高田松原」と東日本大震災津波伝承施設「いわてTSUNAMIメモリアル」。陸前高田市が復興まちづくりで目指したのは、多重防災型まちづくりだ。URは最大12メートルに及ぶ市街地のかさ上げ、移転のための高台造成、避難路の整備などを市と共に行ってきた。市内の高田・今泉の2地区あわせて300ヘクタールという事業規模はURが関わった復興まちづくりでも最大。時間短縮のため「復興CM方式※」に加え、大量の山の土をかさ上げ地へ運搬するためのベルトコンベヤーを導入。これにより想定で8年半かかる工期を約6年短縮した。
すでに引き渡し済みの高田地区には災害公営住宅をはじめ商業施設「アバッセたかた」や公共施設などが建つ。そして本年1月、URが担当した市内のすべての宅地の引き渡しが完了した。
「安全安心かつ景観に配慮したまちづくりを進めてきました。市民の皆さまには大変お待たせいたしましたという思いです。同時に、これだけの規模の事業をお約束の期限内に完了できたことに胸をなでおろしています」
陸前高田復興支援事務所所長の関俊介はそう振り返った。
※受注者が調査、測量、設計および施工の一体的なマネジメントを行う方法。東日本大震災の復興のためにURが作り上げた。
難題に挑んだ今泉地区の造成
最後の引き渡しとなった今泉地区は気仙川から山がそそり立つ平地の少ない地域。津波で低地部は全壊したため、山を造成して高台へ移転した。土の搬出地でもあった今泉地区は造成工事にかけられる期間が短く、かつ三陸沿岸道路(国)や国道45号(国)、国道340号(県)、河川護岸(県)など関連事業者が多いため調整が非常に重要だった。陸前高田市復興局市街地整備課の青山豊英さんは、「市職員に300ヘクタールもの大規模な区画整理の経験がないなか、URさんには関係機関との間に入って調整いただき、円滑に進めていただきました」と話す。地元の人々と話し合いを重ね、歴史があり、味噌や醤油の醸造所が集まっていた震災前のこの地区の雰囲気を残しつつ、防災に強いまちづくりを進めてきたという。
基盤工事を担当したURの柴田敏博は、「地権者の方々、被災者の方々に早く土地をお返しするために、役割分担や工事展開計画には慎重に取り組みました。皆さんのご協力のもと一枚岩で進めることができ、ほっとしています」と語る。雨水・排水がきちんと流れ、かつ災害時でも噴き出すことのない配管や道路の勾配を緻密な計算のもとに進めるなど、目に見えない生活インフラの整備も徹底した。
 陸前高田市職員の青山さん。「かつて伊達藩の代官所が置かれていた今泉地区は歴史と文化のあるまちです。山車をぶつけ合う祭り"けんか七夕"が有名です」
陸前高田市職員の青山さん。「かつて伊達藩の代官所が置かれていた今泉地区は歴史と文化のあるまちです。山車をぶつけ合う祭り"けんか七夕"が有名です」 高田地区をバックに今泉地区の高台に立つURの関(右)と柴田。「市の意思決定が早かったおかげで事業を予定通り終えることができました」
高田地区をバックに今泉地区の高台に立つURの関(右)と柴田。「市の意思決定が早かったおかげで事業を予定通り終えることができました」新たな拠点が誕生
注目の「カモシー」
「山に造成されたまちに、子どもたちの声が響いて、お年寄りがひなたぼっこしていて、すごくいい雰囲気です」と話すのは、今泉で江戸時代から醸造業を営む(株)八木澤商店の河野通洋社長だ。昨年末、今泉に誕生した発酵のテーマパーク「CAMOCY(カモシー)」の立ち上げ先導者でもある。
「今泉を離れた人が帰ってきたときに懐かしいと思える、発酵食品が作られる音やにおいを残しておきたかったんです」と河野さん。
ベーカリーやオーガニックチョコレート工房、ビール醸造所、デリカテッセンなどが入店しているカモシー。ショップオーナーには地元出身者もいれば、震災後に陸前高田と関わり始めた人も。いずれも陸前高田のまち、そして微生物の可能性に共感・賛同した人たちだ。河野さんの感覚では、今泉は震災前、保守的な地域だったという。
「それが津波で全部もっていかれて、仲間がたくさん亡くなって。そこに世界中から助けが入って、新しい仲間が生まれて、新たな挑戦が始まって。今はどう恩返しするかに進んでいます。新しい門が開いた感じで、今後が楽しみです」
市内では市立博物館やワタミオーガニックランドのオープンも控えている。昨年秋にはEVバスの実証実験が行われ、新たなまちで新たな挑戦が始まっている。交流人口が増えれば必要なものも増えるので、新しい仕事をつくることができ、雇用の拡大にもつながる。
「若い人たちは挑戦がおもしろくて仕方ないようです。そしてこのまちには『人口が少なくたっていいんだよ。世界の人口はどんどん増えるんだから、その人たちを受け入れられるまちを今から一緒につくらないか』と子どもたちに言える大人がいるのです」と河野さん。仲間との夢や構想は膨らむ。
カッコイイ大人たちがいる陸前高田は、訪れる人に勇気と優しさをシェアしてくれるまちでもある。
 カモシーで発酵食品を使ったおひつ膳と甘味のお店「発酵食堂やぎさわ」を展開する八木澤商店の河野社長。「うれしいのは、地元の人たちが毎日のように来てくれること。外から知り合いが来たときに、"おらがまちには、カモシーがあるぜ。おいしいものがあるし、面白い人がいるから行こうぜ"と言ってもらえたら最高です」
カモシーで発酵食品を使ったおひつ膳と甘味のお店「発酵食堂やぎさわ」を展開する八木澤商店の河野社長。「うれしいのは、地元の人たちが毎日のように来てくれること。外から知り合いが来たときに、"おらがまちには、カモシーがあるぜ。おいしいものがあるし、面白い人がいるから行こうぜ"と言ってもらえたら最高です」 地元の杉材で建てられたカモシー。名称は、酒や醤油をつくる意味の「醸す」に由来。イートインスペースがある一方、自宅のお鍋を持って総菜を買いに来る人も。貸しスペースでのイベントを楽しみに訪れる人も多い。
地元の杉材で建てられたカモシー。名称は、酒や醤油をつくる意味の「醸す」に由来。イートインスペースがある一方、自宅のお鍋を持って総菜を買いに来る人も。貸しスペースでのイベントを楽しみに訪れる人も多い。【妹尾和子=文、菅野健児=撮影】
特集バックナンバー
UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]
UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。
冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。


![URPRESS 2021 vol.65 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress65/lrmhph000001s0qx-img/header_65.png)