【特集】交流と調査・研究で大学が地域に貢献!原市団地(埼玉県上尾市)
「団地は日本の縮図」「団地の課題は、今後の日本の課題」との考えのもと、芝浦工業大学の学生が地域の課題解決に工学技術を生かして取り組む。
そんな活動が10年以上も続いている団地がある。
石窯で焼くピザが人気の原市カフェ

埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)原市(はらいち)駅から徒歩15分ほどの距離にある原市団地。ここではほぼ毎月「原市カフェ」が開かれている。7月19日の土曜日、カフェのオープン前に到着すると、すでに人が集まっていた。待っている方たちに伺うと、ここのピザがおいしくて、毎月楽しみにしているのだという。お昼には売り切れになってしまうとも。その評判の石窯ピザの準備を進めているのは、さいたま市内に大宮キャンパスを構える芝浦工業大学システム理工学部の学生たちだ。団地の自治会や地元の社会福祉協議会のメンバーも手伝っている。
「ピザ作りの技術は回を重ねるごとに高まっていますし、みんなでワイワイやれるのが楽しい。住民さんも声をかけてくれますので」と学生たちは楽しそう。一方、自治会長の栗田 尚さんは「若い人たちが来てくれると活気が出て、住民の外出のきっかけにもなるし、いろいろ新しい取り組みもしてくれて、ありがたいです」と笑顔だ。
 ラボの前のスペースを利用して開催される原市カフェ。
ラボの前のスペースを利用して開催される原市カフェ。 この日は猛暑日の予報が出るなか、団地内外から多くの人が来店。その場で食べられるテーブルセットも用意されていた。
この日は猛暑日の予報が出るなか、団地内外から多くの人が来店。その場で食べられるテーブルセットも用意されていた。


 この日は上尾高校から3名の女子高生が原市カフェに参加。体験授業としてお手伝い。
この日は上尾高校から3名の女子高生が原市カフェに参加。体験授業としてお手伝い。社会に貢献する人材育成団地はその実践の場
芝浦工業大学が原市団地内に研究拠点「芝浦工業大学サテライトラボ上尾(以降、ラボ)」を構えたのは2014年のこと。以来、同大学のシステム理工学部の作山 康教授が中心となって、地元の人々と交流しながら、学生たちと地域の課題を調査し、解決するための研究活動を続け、地域コミュニティーを盛り上げてきた。原市カフェをはじめ、蔵書を断捨離したいという住民の声を受けて、ラボ内に本棚を造って、みんなに読んでもらえるようにしたり、スマホの使い方講座を開いたり、団地内外にコミュニティーガーデンを整備したり……。他にも、認知症の早期発見センサーを住戸内に設置して検証したり、スマートスピーカーの呼びかけに答えていくとエンディングノートが完成する仕組みを作ったり。
作山教授は取り組みの背景と目的について次のように説明する。
「団地は日本の縮図。団地の課題は、今後の日本の課題でもあります。私どもの大学は、社会に貢献する人材の育成を理念に掲げていまして、原市団地はその実践的教育の場。学生たちは地域の人と触れ合いながら、現場で課題を見つけ、その解決方法を考えます。答えがひとつではないなか、採用される提案をして実践する即戦力を養う。社会に役立つことを実感することで、学生は成長します」
それが可能なのは、学生の提案を自治会の方が真摯に受け止めて、調査・研究に協力してくれる信頼関係あってこそとも語る。
芝浦工業大学と共にまちづくりに取り組むURの森村直子は「作山先生たちは早くから、多様な人々が豊かに暮らすウェルビーイングなまちづくりを掲げ、いろいろな方と連携して活動されています。それぞれの個性を発揮できる温かい雰囲気が魅力で、学生さんもピザの焼き方を後輩に伝授したり、卒業生がイベントに顔を出してくれたりしています」と話す。
 コミュニティーガーデンでブルーベリーの実を摘む作山教授。
コミュニティーガーデンでブルーベリーの実を摘む作山教授。 ブルーベリーはスムージーにして原市カフェで試飲。
ブルーベリーはスムージーにして原市カフェで試飲。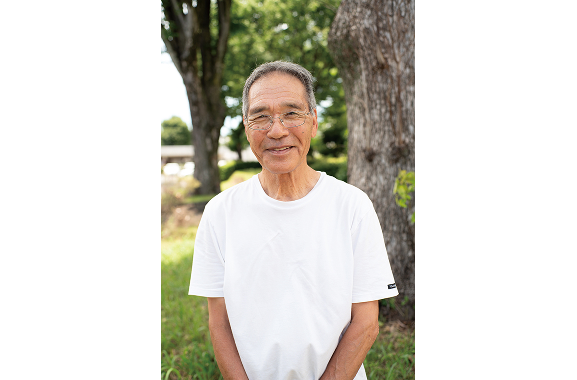 自治会長の栗田さん。
自治会長の栗田さん。 ラボの1階。本棚の前のテーブルセットもこだわりのひとつ。
ラボの1階。本棚の前のテーブルセットもこだわりのひとつ。 サテライトラボの2階には、コミックなどを座って読めるコーナーが設置されている。
サテライトラボの2階には、コミックなどを座って読めるコーナーが設置されている。 原市団地では学生たちの微笑ましい光景を見ることが多いと話すURの森村。
原市団地では学生たちの微笑ましい光景を見ることが多いと話すURの森村。多様な世代のためのリアルな居場所づくり
昨年からはさらに拠点を拡大。地域の方々の意見を取り入れた計画をもとに、学生がラボの2階をDIYで改修し、多世代が気軽に立ち寄り、多様な過ごし方ができる秘密基地のような場を整えた。
大切にしているのは「わくわく・どきどき感」。ディテールにこだわることが小さな幸せや健康につながると考え、ペンキの色や壁紙にも気を配った。ここでは、地域の方による英語に親しむ会や学習支援なども行われている。また、ここで太鼓の演奏をした折には音への配慮を考え、すぐに環境を専門とする学内の他研究室と組み、防音カーテンを設置して騒音測定の検証に着手。
「石橋を叩く前に渡っちゃえ、と走りながら考えている感じです」
そう語る作山先生の行動力や柔軟な発想も、この活動が11年も続いている要因だろう。
今後は高齢者も楽しめるシルバーeスポーツを取り入れ活動量を計測予定。また学生のアイデアを受けて、多世代が共に楽しめるマリオカートを4台揃えてのゲーム大会も開催する。住民の高齢化が進むなか、「孤立化の予防になる居場所になれば」という関係者の願いが集まる場での今後の展開に期待が高まる。
 工具を自由に使える2階のDIYコーナー。
工具を自由に使える2階のDIYコーナー。 ペンキの色にこだわった、サテライトラボの2階の壁。
ペンキの色にこだわった、サテライトラボの2階の壁。 ラボの2階への階段はウィリアム・モリスの壁紙とフランスのペンキでオシャレに。
ラボの2階への階段はウィリアム・モリスの壁紙とフランスのペンキでオシャレに。 1966(昭和41)年に管理開始した原市団地。外壁塗装や外付けエレベーターの設置などを実施している。
1966(昭和41)年に管理開始した原市団地。外壁塗装や外付けエレベーターの設置などを実施している。【妹尾和子=文、菅野健児=撮影】
- Xポスト(別ウィンドウで開きます)
- LINEで送る(別ウィンドウで開きます)
特集バックナンバー
UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]
UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。
冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。


![URPRESS 2025 vol.83 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress83/rquj5t00000053s6-img/header_83.png)



