【特集】住民主体で防災集団移転が進むまち(茨城県大洗町涸沼川 那珂川水系)
夏には海水浴客でにぎわう大洗サンビーチ海水浴場を擁する茨城県大洗町。
那珂川の支流である涸沼川による浸水被害を受けてきた地区がスピード感をもって防災集団移転促進事業を進めている。
たびたびの水害から安全な暮らしへ
 茨城県の関東唯一の汽水湖、涸沼を持つ涸沼川。ご覧の通り住宅が川に隣接して建っている。令和元年の水害は、増水した那珂川の水が涸沼川に流れ込んだバックウォーター現象で起こった。
茨城県の関東唯一の汽水湖、涸沼を持つ涸沼川。ご覧の通り住宅が川に隣接して建っている。令和元年の水害は、増水した那珂川の水が涸沼川に流れ込んだバックウォーター現象で起こった。茨城県大洗町・水戸市とひたちなか市の境界を流れ、太平洋へと注ぎ出る那珂(なか)川。涸沼(ひぬま)川は、この那珂川水系のひとつで、那珂川の下流域に流れ込んでいる。
江戸時代には東北諸藩が那珂川の河口に開けた涸沼川の湊まで船を進め、ここから物資を江戸に送った歴史がある。そのかつての舟運の湊だったあたりが、現在の大洗町堀割・五反田周辺地区。今回、全国に先駆けて、事前防災としての防災集団移転促進事業(以下、防集事業)を進めているまちだ。
この一帯は令和元年東日本台風をはじめ、過去に何度も浸水被害を受けてきた。河川を管理する関東地方整備局常陸河川国道事務所の小平武志さんに、これまでの治水事業を伺った。
令和元年の甚大な被害を受け、『那珂川緊急治水対策プロジェクト』がまとめられ、対策が進むなか、2021(令和3)年に『那珂川水系流域治水プロジェクト』が動き出しました。ここから災害を未然に防ぐために家屋を移転させる防集事業を含めた、防災まちづくりの検討が始まったのです」
 大洗港は苫小牧との間にフェリーが運航、首都圏、北関東と北海道を結ぶ物流拠点となっている。
大洗港は苫小牧との間にフェリーが運航、首都圏、北関東と北海道を結ぶ物流拠点となっている。 涸沼川に架かる鉄橋を走る鹿島臨海鉄道。
涸沼川に架かる鉄橋を走る鹿島臨海鉄道。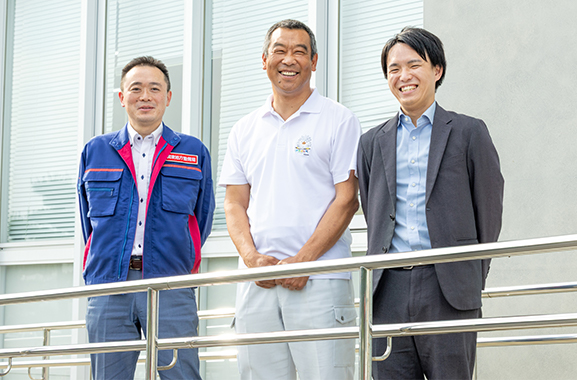 お話を伺った、左から関東地方整備局の小平さん、大洗町の木村さん、URの小松﨑。
お話を伺った、左から関東地方整備局の小平さん、大洗町の木村さん、URの小松﨑。URのノウハウを防集事業に注ぎ込む
堀割・五反田周辺地区の皆さんに行った意向調査では、8割の方が水害の危険を認識し、8割の方が条件によっては移転したいという結果が出た。
「そこで住民の皆さんと『防災まちづくり』の検討会を始めたのですが、なかなか方向性がまとまりませんでした。この事業は住民が移転したい意志を示し、それを受けて町が手続きをするプロセスが大切なのですが、町は人手も足りませんし、話し合いを進めるノウハウもありません。そこでURさんに支援を依頼したのです」と大洗町都市建設課の木村成利さんが説明する。
UR災害対応支援部でこの事業に関わる小松﨑裕輔は、「これまでURが他の事業で培ってきたノウハウをここに展開し、木村さんには、まず地元のキーマンを見つけましょうとアドバイスしました」と話す。
木村さんは、「皆さんとの話し合いの席で、中心になってくださる方はいませんかと聞いていくと、グループのリーダー的な方が出てきました。皆さん、この事業への関心は高く、自分なりに勉強している方もいらっしゃいます。高齢者も多いのですが、3人のリーダー的な方が生まれ、その方たちを中心に丁寧な対話を進めた結果、皆さんの意向が防集事業にまとまっていきました」と振り返る。
住民との話し合いの席では、椅子を円形に置いて、住民同士が顔を見ながら話すスタイルに変えた。
「例えば『説明会を開催します』というと町主導になりますが、『説明会が開催されます』といえば、住民が主体になります。このように住民主体のマインドを醸成するためのアドバイスもさせてもらいました」とURの小松﨑。その結果、防災を自分ごととして考えるようになり、住民の意見がまとまっていったのは言うまでもない。
「URさんが、『一緒に悩んで考えましょう』と言ってくれた言葉が忘れられません。事前防災として既成市街地の空き地や空き家を活用した防集事業は、全国初の事例です。誰も経験がない事業計画の大臣同意までの事務的なプロセスにも、URさんの力をお借りしました」と木村さんは言う。
24年6月、大臣同意を得て、防集事業が進み始めた同地区。全72戸のうち、38戸が隣接する市街地の空き地や空き家を利用して移転、残りの34戸は個別に移転する。住民たちは、「高齢者も多いので、市街地への移転は3年で目途をたてよう」とスピード感をもって事業を進める姿勢を共有している。
関東地方整備局の小平さんは、「これからもスピード感をもって町やURさんと連携して事業を進めていきたい」と話す。
大洗町の木村さんは、「今後も事業を進めるなかでさまざまな課題が出てくるでしょうが、一つひとつに丁寧に対応し、移転した皆さんが、移転してよかったと思えるまちづくりをしていきたい」と締めくくった。
 涸沼川ではしじみ漁も行われており、この地区には漁業従事者や飲食店もある。皆さんそれぞれの事情を抱えながらも、防災事業が進められている。
涸沼川ではしじみ漁も行われており、この地区には漁業従事者や飲食店もある。皆さんそれぞれの事情を抱えながらも、防災事業が進められている。 移転後の跡地利用はまだ白紙だが、URの小松﨑は、「移転した人たちが、移転してよかったと思えるような跡地利用をして、またその場所で皆さんがつながれるようにしたい」と話す。
移転後の跡地利用はまだ白紙だが、URの小松﨑は、「移転した人たちが、移転してよかったと思えるような跡地利用をして、またその場所で皆さんがつながれるようにしたい」と話す。 茨城県有数の観光地である大洗町。町の木村さんは、「大洗町の人々は、みんな親戚のようなもの。堀割・五反田周辺地区の皆さんも、隣接する市街地への移転なら、違和感なく新しい暮らしが始められると思います」と言う。
茨城県有数の観光地である大洗町。町の木村さんは、「大洗町の人々は、みんな親戚のようなもの。堀割・五反田周辺地区の皆さんも、隣接する市街地への移転なら、違和感なく新しい暮らしが始められると思います」と言う。 令和元年の水害をきっかけに、茨城県、水戸市、国と、大洗町(オブザーバー)、URがアドバイザーとして参加して「流域治水ワークショップ」が立ち上がった。河川整備とまちづくりを一体的に進めるための、意見交換や情報共有が目的だ。
令和元年の水害をきっかけに、茨城県、水戸市、国と、大洗町(オブザーバー)、URがアドバイザーとして参加して「流域治水ワークショップ」が立ち上がった。河川整備とまちづくりを一体的に進めるための、意見交換や情報共有が目的だ。 令和元年の浸水状況。
令和元年の浸水状況。【武田ちよこ=文、青木 登=撮影】
特集バックナンバー
UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]
UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。
冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。


![URPRESS 2025 vol.82 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress82/rquj5t0000000sfy-img/header_82.png)



