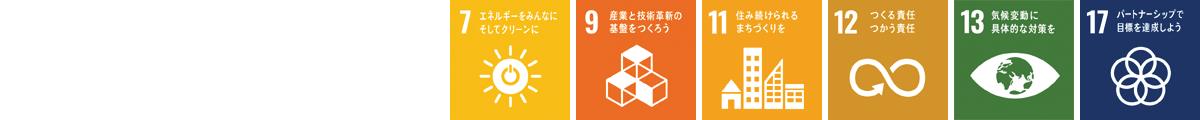【URのまちづくり最前線 第16回】弥生町三丁目周辺地区 密集市街地整備事業 (東京都中野区)
防災性の向上で地域の魅力アップ!
「住みたくなるまち」に
各地で防災性の強化を通して「住みたくなるまち」づくりに取り組んでいるUR。
弥生町三丁目周辺地区では、土地区画整理をはじめ避難道路整備支援などの防災性向上に向けた
取り組みを中野区と一緒に進め、地域の活性化や住宅地としての魅力アップを目指している。
昨年10月31日にまちびらきが行われてから半年、新たな息吹あふれる現地を訪ねた。
 都営アパートの跡地につくられた川島公園。防災パーゴラ、防災倉庫、ソーラー式照明灯、ソーラー時計などが備えられている。
都営アパートの跡地につくられた川島公園。防災パーゴラ、防災倉庫、ソーラー式照明灯、ソーラー時計などが備えられている。木造住宅の密集エリアの課題解決に向けて
東京メトロ丸ノ内線で新宿から6分、下車した中野新橋駅から7分ほど歩いた先に目的地の川島公園はあった。住宅地のなかに突然現れた、ふわっと開けた空間で子どもたちが走り回り、しゃぼん玉で遊んでいた。その様子に柔らかな眼差しを注ぐ、近隣の人の姿もあった。ここは中野区が取り組む弥生町三丁目周辺地区の防災まちづくりの一環として整備された、防災機能をもつ公園。災害時の利用も考慮しているため、防災井戸やパーゴラテントなどが装備されている。
「もともとこの地域は道幅の狭い道路や、行き止まり道路が多く、災害時の危険性が高いことから、防災性の向上が課題でした」と話すのは防災まちづくりを担当する中野区の久保誠さん。道路幅が狭く緊急車両が入れないため、区では「避難用の道路ネットワークの整備」や「消防車が入れる幅員6メートルの避難路の確保」「沿道の建物の不燃化促進」などが課題となっていた。
中野区とまちづくりの基本協定を結んでいるURは、2016(平成28)年から区の要請を受けて都営川島町アパート跡地の土地区画整理事業に着手。避難道路や公園、集合住宅を整備するなど、中野区と共に防災性の向上と居住環境の改善を進めてきた。
久保さんと共に防災まちづくりを担当している中野区の一松裕美さんが、整備前の同じ場所の写真を広げながら「この先にあった住居の方に移転していただき、道路を延ばしました。新宿の高層ビルまで見えるようになりました」と説明してくれた。弥生町三丁目周辺地区では現在も避難道路の整備を進行中。最終的には9本の避難道路が整備される予定だ。電線を地中化し、拡幅と同様の効果を得るため道路脇の電柱を撤去する準備も進んでいる。
あって当たり前のように思いがちな道路も、都心の住宅が密集する地域で新たにつくるには、道路や公園などの用地確保のための移転をはじめ多くの人の協力や働きが不可欠で、手続きも膨大だ。
「防災まちづくりのために、住み慣れた場所を離れなければならない方の生活再建を第一に考えながら進めてきました。結果的に道路や公園が完成して、住民の方の利便性は確実に高まっていると思います」と久保さん。
道路整備のための権利者との協議を担当するURの宮﨑真美は言う。
「第二の故郷といったら大げさかもしれませんが、道で会えば声をかけていただいたり、あいさつを交わす方が増えました。何代もの先輩が続けてきた協議を受け継いでいる責任は大きいですが、権利者さんの思いを少しでも汲み上げられるように努めています」
共に協議に臨むことの多い一松さんは、「URの方は専門知識や経験が豊富で、権利者さんからの質問にその場で答えてくださるので時間の無駄がなく、とてもありがたいです」と話す。
 園内には防災井戸もあり、汲み上げた水をマンホールトイレの貯水槽につなげられる仕組み。
園内には防災井戸もあり、汲み上げた水をマンホールトイレの貯水槽につなげられる仕組み。 マンホールトイレ用のトイレテントを設置するための固定アンカーも装備されている。
マンホールトイレ用のトイレテントを設置するための固定アンカーも装備されている。 左から中野区の久保さんと一松さん、URの伏見と宮﨑。アイデアを出し合いながら連携し、魅力的なまちづくりを進めている。
左から中野区の久保さんと一松さん、URの伏見と宮﨑。アイデアを出し合いながら連携し、魅力的なまちづくりを進めている。
 2019年10月31日に開催された「弥生町三丁目地区まちびらき式」。中野区の酒井直人区長をはじめ、UR東日本都市再生本部長の田中伸和もあいさつし、テープカットを行った。
2019年10月31日に開催された「弥生町三丁目地区まちびらき式」。中野区の酒井直人区長をはじめ、UR東日本都市再生本部長の田中伸和もあいさつし、テープカットを行った。「ボトムアップ」と 「バリューアップ」
移転してもらう方の代替地や住まいの提案、確保も大切な仕事だ。URは川島公園の近くに代替地を用意し、賃貸の集合住宅「コンフォール中野新橋」も建設した。
「コンフォール中野新橋」は1階の住戸に花台やテラスを設け、バルコニー側にも出入口がある珍しい造り。まちへの愛着を育んでもらえるように景観の統一を心がけ、立ち話ができるようなスペースを建物の周囲に確保。四季折々の花や果実が楽しめるような植栽にした。
「ご近所との交流やグリーンを楽しむ住宅地を目指して、防災まちづくりにご協力いただく方が移転後もこれまでと同様の暮らしやご近所づきあいが継続できるように心がけました」
と説明するのは、URの建築担当の伏見沙和子。結果として、道ゆく人から「ここに住みたいね」という声が聞こえてくるまちなみが形成されつつある。
防災性の向上である「ボトムアップ」に加え、地域の潜在的な価値を見出して魅力を高める「バリューアップ」を目指し、安全・安心で暮らしやすい密集市街地の整備に取り組むUR。ここ弥生町三丁目周辺地区でも「住みたくなる・住み続けたくなるまち」づくりを進めている。

 27戸が入るコンフォール中野新橋。中野新橋駅寄りにエントランスを配置し、その周囲に地域に開いたスペースを設けている。季節を彩る植栽の成長が楽しみだ。
27戸が入るコンフォール中野新橋。中野新橋駅寄りにエントランスを配置し、その周囲に地域に開いたスペースを設けている。季節を彩る植栽の成長が楽しみだ。 地域の避難場所である東京大学教育学部附属中等教育学校方面への道路の拡幅が進められている。拡幅している部分とこれからの部分がある。
地域の避難場所である東京大学教育学部附属中等教育学校方面への道路の拡幅が進められている。拡幅している部分とこれからの部分がある。 整備前。中野新橋駅からの幹線道路に面して建物があり、奥の住宅地に入ることはできなかった。
整備前。中野新橋駅からの幹線道路に面して建物があり、奥の住宅地に入ることはできなかった。 建物が取り壊され、新たに道路が整備された。通り抜けが可能となり、防災性と利便性が高まった。
建物が取り壊され、新たに道路が整備された。通り抜けが可能となり、防災性と利便性が高まった。【妹尾和子=文、青木登=撮影】
URのまちづくり最前線 バックナンバー
UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]
UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。
冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。


![URPRESS 2020 vol.61 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress61/lrmhph000001ez4z-img/header.png)