復興の「今」を見に来て!第16回 Part1 岩手県岩泉町
 急激な雨量の増加と水位の急上昇によって、堤防を越えた岩泉町の小本(おもと)川。河道の掘削や築堤、護岸、橋梁の架け替えなど、復旧・復興作業が続く。
急激な雨量の増加と水位の急上昇によって、堤防を越えた岩泉町の小本(おもと)川。河道の掘削や築堤、護岸、橋梁の架け替えなど、復旧・復興作業が続く。台風被災からの復興の土台づくりをサポート
 被災当時の流木が押し寄せた岩泉上町地区
被災当時の流木が押し寄せた岩泉上町地区 道路が崩れた県道久慈岩泉線
道路が崩れた県道久慈岩泉線2011(平成23)年の東日本大震災で被災した岩泉町。この町をさらに台風10号が襲ったのは、2016(平成28)年8月30日のことだった。豪雨による河川の氾濫や土砂災害で多くの人命が失われるとともに、河川や道路などのインフラをはじめ、家屋や施設にも甚大な被害が及んだ。
被害は水の豊かな町の全域に
縁深い森と豊かな泉に抱かれた岩泉町は、本州最大の広さをもつ町だ。その全域にわたる被害を前に、いったいどこから手をつけていいのか? 町の人々は途方に暮れたという。自然災害では、いかに初動を早くするかがポイント。町のマンパワーが限られるなか、岩泉町からの支援要請を受けたURは、復興まちづくり計画策定のための助言や技術提供などを担当。復旧のための工事発注者支援をするグループ会社のURリンケージと共に、町の早期復旧・復興に向けて尽力してきた。
被災した年の11月にURから岩泉町に派遣され、昨年4月より副町長を務める末村祐子は、日が経っても次々とあちこちで被害が明らかになる状況に驚いたという。
「毛細血管のように町土全体に張り巡らされた川や沢、その随所で被害が起きたのです」
経験を生かして町に寄り添う
 災害公営住宅は63戸。URは復興まちづくりを事業情報の提供や、考え方への助言などで支援。建物の建設は岩泉町で行った。
災害公営住宅は63戸。URは復興まちづくりを事業情報の提供や、考え方への助言などで支援。建物の建設は岩泉町で行った。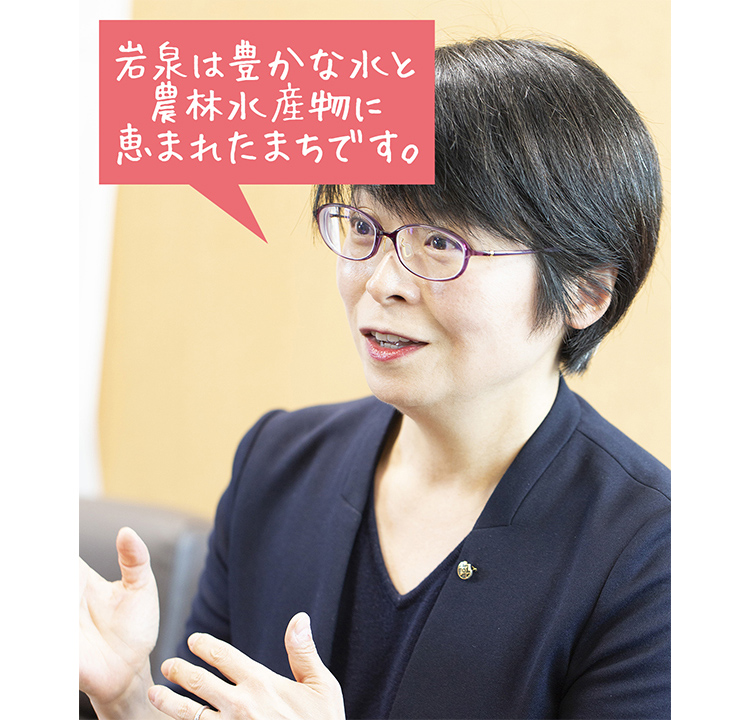 被害の全体像を把握するのが大変だったという末村祐子副町長。
被害の全体像を把握するのが大変だったという末村祐子副町長。 龍泉洞は観光名所でもある鍾乳洞。世界有数の透明度を誇る地底湖や鍾乳石が造り出す神秘的な岩肌に圧倒される。
龍泉洞は観光名所でもある鍾乳洞。世界有数の透明度を誇る地底湖や鍾乳石が造り出す神秘的な岩肌に圧倒される。復興まちづくりを進めるうえで大変役に立っているといわれるのが、URが作成した「災害復旧ロードマップ」だ。
「町内の6つの地域ごとに、地図上に災害箇所と工事の予定などを書き込んだもので、いつ、どこで、どのような復旧工事が行われるのかを目に見えるかたちにしたものです」
と末村副町長は説明する。このマップにより、町の人たちに復旧工事の進捗をわかりやすく伝えられるようになったと喜ばれた。また今後の備えの意味でも、災害箇所の貴重な記録となっている。
何が大切なのか、どんな選択肢がありえるのか、特に国の事業の情報提供などで、町の職員を支えることを心がけたURの職員たち。
「こうした対話は、復旧・復興を通じ、より災害に強い地域をつくろうとする職員の情熱を後押しし、町民に安心いただけるまちづくりの基礎になったと思っています」
と末村副町長。復興まちづくりを主導してきた中居健一町長も「豪雨災害に関する膨大な復旧工事や復興まちづくりを短期間で集中的に進める上で、震災復興など経験豊富なURグループの協力が得られ、安心感がありました」と話す。
建物被害は1916棟。河川が133カ所被災するなど、町の復旧・復興に要する経費が東日本大震災の10倍以上に及ぶ甚大な被害。町の基幹である農林水産業、それを6次産業化で支える岩泉ヨーグルトをはじめとする乳製品、日本三大鍾乳洞のひとつ、龍泉洞の水を使った珈琲や化粧水、日本一の生産量を誇る山わさびの生産など、町では産業経済の再生にもいち早く着手。販路が途切れることのないように、施設の迅速な復旧のための対応に努めた。
このような取り組みの結果、一部を除き、被災からほぼ一年で工事発注の目途が立ち、現在も順次、復旧・復興工事が進められ、活気が戻ってきている。
さらに岩泉町では、災害時、こきざみに変化していく状況や情報を集約し、正しくタイムリーに把握、発信すべく、昨年度、危機管理課を設置。各地の自主防災組織と連携がとれる体制を整備している。昨年は町民を含め防災士の資格を約60名が取得するなど防災意識も高まっている。いつ、どこで、何が起こるかわからない今の時代、備えにも力を入れ、まちの再生に向かって進む岩泉町だ。

【妹尾和子=文、菅野健児=撮影】
復興の「今」を見に来て!バックナンバー
UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]
UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。
冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。


![URPRESS 2019 vol.58 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress58/lrmhph000000zhte-img/header.png)