特集:団地を超えて「まち」へ 新しいまちの魅力づくりへの挑戦が始まっている > ひばりが丘パークヒルズ
建て替えを機に
多世代がつながるまちが生まれた
ひばりが丘パークヒルズ 東京都西東京市、東久留米市
約60年前、当時最先端の住まいとして誕生したひばりが丘団地。
建て替えを機に、民間デベロッパーとパートナーの関係を結び、多様な世代の人々が生き生きと暮らす、新しいまちが生まれている。
 高層に建て替えて集約し、ひばりが丘パークヒルズとして生まれ変わった団地。松やケヤキなどの緑が豊かに残り、団地全体が大きな公園のような雰囲気だ。
高層に建て替えて集約し、ひばりが丘パークヒルズとして生まれ変わった団地。松やケヤキなどの緑が豊かに残り、団地全体が大きな公園のような雰囲気だ。生まれ変わったひばりが丘団地
敷地の中央を東西に貫くけやき通りを見渡して、建て替えられたひばりが丘団地のゆったりと広い空間と木々の豊かさに圧倒された。車路に沿ってケヤキの大木が20メートルほどの高さまで枝を伸ばし、その背後には舗道、さらにベンチを配した緑地が広がっている。通りと緑地をはさんで立つ住棟は12階建てだが、50~60メートルもの間隔があって圧迫感はまったくない。樹木と高層住宅が調和した、美しいまちなみが広がっていた。
西武池袋線ひばりヶ丘駅から徒歩なら約15分、バスで約6分。西東京市と東久留米市にまたがる約33・9ヘクタールもの広大な敷地に、ひばりが丘団地が誕生したのは1959(昭和34)年。戸数2714戸の首都圏初の大規模団地は、当時最先端のモダンな間取りと設備を備え、団地内には公園や野球場、学校、スーパーなどがつくられて、その後の団地の手本になった。
この「憧れの団地」も40年以上がたち、UR都市機構は1999年から団地再生事業に着手。樹木など既存の環境資源を生かし、緑と十分な空間を確保したまちづくりと、団地の歴史を継承することを基本方針として、まず賃貸住宅の建て替えを実施。2012(平成24)年に完了、ひばりが丘パークヒルズに生まれ変わった。
さらにこの団地再生事業では、新しい時代を開く画期的な取り組みが進められた。「民間事業者と連携してのまちづくり」と、多様な世代が生き生きと暮らし続けられる「ミクストコミュニティの形成」だ。
 昭和30年代後半のひばりが丘団地。約33.9haに2~4階建ての住棟が184棟。建設当時は最先端の建物として注目され、皇太子(当時)ご夫妻をはじめ、たくさんの要人が視察に訪れた。
昭和30年代後半のひばりが丘団地。約33.9haに2~4階建ての住棟が184棟。建設当時は最先端の建物として注目され、皇太子(当時)ご夫妻をはじめ、たくさんの要人が視察に訪れた。【写真/日刊建設工業新聞社】
事業パートナー方式で新しいまちづくり
これまでの4階建てと2階建てを高層化したことで、敷地には広大な土地が生まれた。ここに高齢者や子育てを支援する公共公益施設を誘致。住宅地として譲り渡すことになった約7ヘクタールの土地に関しては、エリア全体の価値を向上させるためにUR都市機構と連携し、協議のうえで開発を進める民間事業者を募る、UR初の「事業パートナー方式」を取り入れている。
「街区ごとに雰囲気が異なるパッチワークのようなまちにならないよう、民間事業者の発想・ノウハウを活用しながら、調和したまちづくりを目指しました」とUR都市機構ストック事業推進部主幹の木村仁紀は言う。
UR都市機構と事業パートナーとなった民間デベロッパーとで団地再生協議会を発足させ、話し合いを行いながら開発計画を練っていったが、さらに一歩踏み込んで取り組んだのが「エリアマネジメント」の推進だった。
エリアマネジメントとは地域の環境や価値を維持・向上させる、住民を中心にした主体的な取り組み。まずUR都市機構と民間デベロッパーでエリアマネジメントの実施組織として、一般社団法人まちにわ ひばりが丘を設立した。
地域の住民自身の手でまちに「和」をつくる


 建て替えに際し、長屋形式の2階建て住宅「テラスハウス」118号棟を残した。この内部を改修して、住民同士の交流の場「ひばりテラス118」が誕生。
建て替えに際し、長屋形式の2階建て住宅「テラスハウス」118号棟を残した。この内部を改修して、住民同士の交流の場「ひばりテラス118」が誕生。「ひばりテラス118」には、カフェ「COMMA,COFFEE」(写真上)や自由に使えるコミュニティースペースがつくられた。
敷地の西側の端に、レトロな2階建ての建物がある。UR都市機構が残した旧団地のテラスハウスだ。まちにわ ひばりが丘が改修してエリアマネジメントの拠点「ひばりテラス118」が誕生。内部はおしゃれに改装され、友人同士の集まりや教室などに利用できる大小6つのコミュニティースペースや、コーヒーや軽食を提供するカフェもあり、敷地内に住む人だけでなく、誰でも利用が可能だ。
ここではベビーマッサージ講座やアロマや書道、英会話、ヨガの教室など、さまざまな催しが開かれている。また、乳幼児連れのママを対象に、手遊びや工作などをする「まちにわリビング」やカフェでの「バーイベント」、「ジョギング会」といった、まちにわや住民が企画するイベントも行われている。
こうしたまちにわ独自のイベントを担っているのが、「まちにわ師」の面々だ。まちにわ師とは住民を主役にした活動をサポートするボランティアで、養成講座を経て誕生。ひばりテラス118の運営や季刊紙AERUによる情報発信などにも腕を振るう。2015年11 月のテラスのオープン以来、2016年末までに3期の募集が行われ、約30名が活動している。年齢も住まいの場所もさまざまだが、「地域に貢献したい」「まちをよくしていきたい」という思いは共通だ。 「地域のために何かしたいと思っていても、ゼロから自分で始めるのは難しい。募集は渡りに船でした」 と一期生の岩穴口(いわなぐち)亜紀さん。 「エリアの人と交流できると思って応募しました」
同期の西田淳子さんはいう。
まちにわ ひばりが丘の運営は、コミュニティーづくりが専門の企業に委託しているが、自主的な活動を軌道に乗せて2020年には住民の手に運営を委ねる予定だ。それを見据え、活動を裏方で支える事務局スタッフもなるべく地域の人を採用するようにしている。 「ただワイワイみんなで楽しくやるのではなく、最終的には子育てや高齢化などの課題の解決を図り、困ったときに助け合える関係をつくっていくことが活動の目的です。住民の皆さんがどんどん自主的に取り組んで、僕の存在が早く不要になってほしいですね」
そう事務局長の高村和明さんは語っていた。
オープンから1年以上がたった今、催しに参加する人、ふらりと来てまちにわ師とおしゃべりする人など、来訪者はひきもきらない。特に乳幼児を抱えるお母さんたちには「ここに来れば誰かがいる、何か話せる」場として定着している様子だ。今後の課題はいかに幅広い世代の方々に関わってもらうか。スタッフもまちにわ師も、団地自治会との連携なども含めて、策を考える毎日だという。
 戸外で行われたまちにわ主催のイベント
戸外で行われたまちにわ主催のイベント 「ひばりテラス118」で開催されたアロマ教室。エリア外からの参加者も多い。
「ひばりテラス118」で開催されたアロマ教室。エリア外からの参加者も多い。 まちにわ ひばりが丘のスタッフ、青木留美子さん(右)と中島衣里さん。2人とも関西出身で、「この仕事を通してたくさんの人と知り合いになれたことがうれしい」と話す。
まちにわ ひばりが丘のスタッフ、青木留美子さん(右)と中島衣里さん。2人とも関西出身で、「この仕事を通してたくさんの人と知り合いになれたことがうれしい」と話す。 まちにわ師の西田淳子さん(右)と岩穴口亜紀さん。岩穴口さんはこの団地で生まれ育った。ここに来ると知り合いにも会えるので、毎日立ち寄っている。制作中の折り紙は、入口に飾る。
まちにわ師の西田淳子さん(右)と岩穴口亜紀さん。岩穴口さんはこの団地で生まれ育った。ここに来ると知り合いにも会えるので、毎日立ち寄っている。制作中の折り紙は、入口に飾る。 昭和30年代に建設された「スターハウス」(手前)は、上空から見ると星形のユニークな建物。建て替え時に1棟だけ残し、現在は管理サービス事務所に。生活支援アドバイザーもここに常駐。
昭和30年代に建設された「スターハウス」(手前)は、上空から見ると星形のユニークな建物。建て替え時に1棟だけ残し、現在は管理サービス事務所に。生活支援アドバイザーもここに常駐。 まちにわ ひばりが丘の事務局長・高村和明さん。「URと民間デベロッパーが一緒になったひばりが丘だから、できることがある」と話す。
まちにわ ひばりが丘の事務局長・高村和明さん。「URと民間デベロッパーが一緒になったひばりが丘だから、できることがある」と話す。多世代が生き生きと暮らし続けられるまちへ
一方、団地を中心に地域の高齢化が急速に進んでいることを背景に、UR都市機構は団地の地域医療福祉拠点化を進めている。これは行政や地域の方々と連携しながら、介護・医療・子育てなどのサービスや支援体制の充実、多様な世代に対応した居住環境の整備、多世代のコミュニティー形成を図っていくもの。団地では地域包括支援センターを中心に関係者が定期的に集まり、高齢者支援の情報共有や課題解決を図り、高齢者の相談対応や安否確認を行う生活支援アドバイザーを配置した。
さらに、高齢者が要介護状態になっても地域に住み続けられる基盤をつくるため、UR都市機構は(株)日本生科学研究所と共同で、診療所やサービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能ホーム、グループホームなどを集めた「日生ケアヴィレッジひばりが丘」を整備。ここでは団地に住み続けながら利用できる24時間の生活支援サービスも用意している。
「子どもから子育て世代、高齢者まで多世代が自然につながりを共有できる拠点になりたいと思っています。何か困ったときに気兼ねなく相談できる関係を築き、住み慣れた場所で安心して住み続けられるまちにしたい」とケアヴィレッジを統括する後藤 誠さんはいう。
ひばりが丘では子育て世代への支援も手厚い。
「団地はまさに地域の拠点。活動の場があり、地域に必要なサービスがあり、人材の宝庫でもあります。それらを活用し、うまくつなげながら、団地を含む地域一体で多様な世代が生き生きと暮らし続けられるまち(ミクストコミュニティ)の実現を目指したい」(UR 都市機構多摩エリア経営部主幹・山地将人)
 団地の南側には、地域の在宅介護・医療の拠点となる「日生ケアヴィレッジひばりが丘」がある。エレベーターを増築し、住棟全体をバリアフリー化したサービス付き高齢者向け住宅は、常に満室だ。
団地の南側には、地域の在宅介護・医療の拠点となる「日生ケアヴィレッジひばりが丘」がある。エレベーターを増築し、住棟全体をバリアフリー化したサービス付き高齢者向け住宅は、常に満室だ。 エリア長として全体を統括する後藤 誠さん。
エリア長として全体を統括する後藤 誠さん。 ひばりが丘の団地再生事業を担当しているUR都市機構東日本賃貸住宅本部のメンバー。右から木村仁紀、山地将人、村田史子、清水真道。エリアマネジメントの取り組みは2016年度グッドデザイン賞を、団地再生事業は2016年都市住宅学会賞業績賞を受賞した。
ひばりが丘の団地再生事業を担当しているUR都市機構東日本賃貸住宅本部のメンバー。右から木村仁紀、山地将人、村田史子、清水真道。エリアマネジメントの取り組みは2016年度グッドデザイン賞を、団地再生事業は2016年都市住宅学会賞業績賞を受賞した。新しい時代を開くモデルケースに
ひばりが丘団地には、60年近い歴史と実績を誇る自治会がある。周辺から多くの来場者を集める夏祭りやバスハイク、食事会など、今も活発な活動を続けている。昔からお住まいの方々の交流は密で、半世紀以上自主運営する幼児教室を通じ、子育て世代との協力体制も良好だという。
昨年から日生ケアヴィレッジの若い職員や、まちにわの方が祭りを手伝ってくれて大いに助かったと、自治会事務局長の井埜(いの)光一さんはいう。 「今後は、まちにわさんや民間マンションに住む皆さんと、祭りを共同で開催できればと思っています」
UR都市機構やパートナー事業者がハードを整備し、コミュニティーづくりの専門家も加わって種を蒔き、地域の人々がつながりながら力強く育とうとしているこれらの取り組み。団地にとどまらず周辺地域にも波及するものとして、また他の団地の先鞭をつけるモデルケースとしても注目されている。60年前、団地という新時代の住まいと暮らしを創ったひばりが丘で、今また展開するミクストコミュニティへの壮大な取り組みは、明日を切り開く大きな力となるだろう。
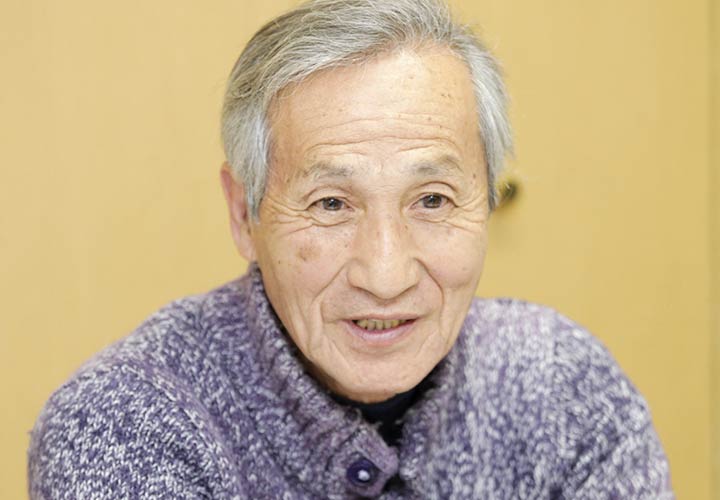 ひばりが丘団地自治会事務局長の井埜光一さんは、この団地に住んで44年。
ひばりが丘団地自治会事務局長の井埜光一さんは、この団地に住んで44年。
【西上原三千代=文、佐藤慎吾=撮影】
動画

建て替えを機に多世代がつながるまちが生まれた
約60年前、当時最先端の住まいとして誕生したひばりが丘団地。
建て替えを機に、民間デベロッパーとパートナーの関係を結び、多様な世代の人々が生き生きと暮らす、新しいまちが生まれている。

部屋が変われば団地が変わり、まちが変わる!
大阪市大正区にある千島団地は、区役所や公園に隣接した、まちの中心地に立つ2236戸の大型団地。
築44年が過ぎて高齢化が進み、空き住戸も増えている。
ここで大正区と民間業者も巻き込んで、DIYでまちと団地を活性化させる新たな試みがスタートした。

昭和30年代のひばりが丘団地に江戸東京博物館でタイムスリップ!
フリーアナウンサーの永井美奈子さんが、江戸東京博物館を訪ねた。お目当ては、高度経済成長期の集合住宅の暮らしを再現した展示の見学だ。
UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]
UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。
冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。


![URPRESS 2018 vol.48 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress48/lrmhph000000nsth-img/bnr_maintitle_pc.png)

