背景・特徴
背景・特徴
「米百俵プレイス」とは
「米百俵」の由来
明治初年、戊辰戦争に敗れた長岡藩は貧困と飢餓の中にいました。そこに救援のために届けられた米を、大参事・小林虎三郎は、周囲の反対を押し切って売却し、国漢学校の設立資金に充てました。国漢学校から多くの優れた人材が育ち、長岡や日本の発展の礎を築きました。この「人づくりはまちづくり」という「米百俵の精神」は長岡に脈々と受け継がれています。
「米百俵」の故事は、山本有三の戯曲によって広く知られるようになり、小泉純一郎元首相も所信表明演説で引用しました。
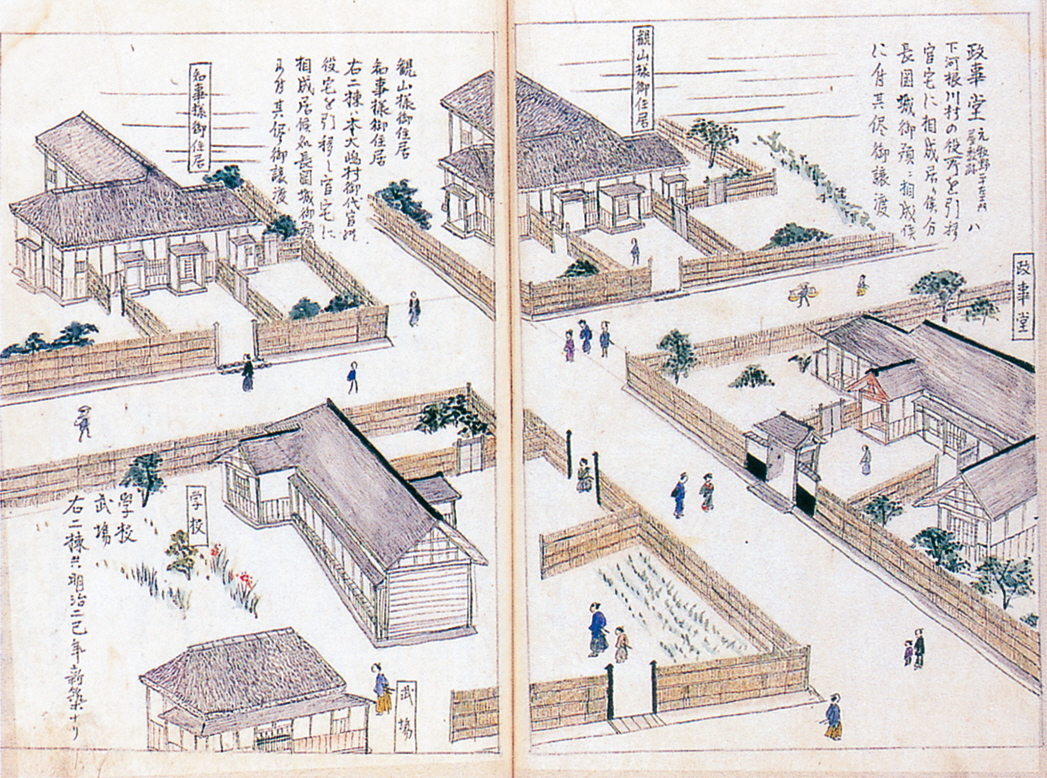 明治初年の大手通りの様子が描かれている「懐旧雑誌」 左の「知事様御住居」と「学校」が「米百俵プレイス」の場所
明治初年の大手通りの様子が描かれている「懐旧雑誌」 左の「知事様御住居」と「学校」が「米百俵プレイス」の場所
「米百俵プレイス」が目指すもの
100年先の長岡のための人づくりの場、産業振興の拠点。ここから賑わいを生み出す
現在再開発中の土地は、「米百俵」の故事から生まれた国漢学校跡地であり、「米百俵の精神」を今に伝える歴史的な場所です。
この地の歴史と精神を継承し、知的創造、人材育成、産業基盤を強化する場として、未来の長岡を支える人づくり・学びの拠点を目指します。
特徴(1)「米百俵プレイス ミライエ長岡」について
「米百俵プレイス ミライエ長岡」については長岡市のページもご覧ください。
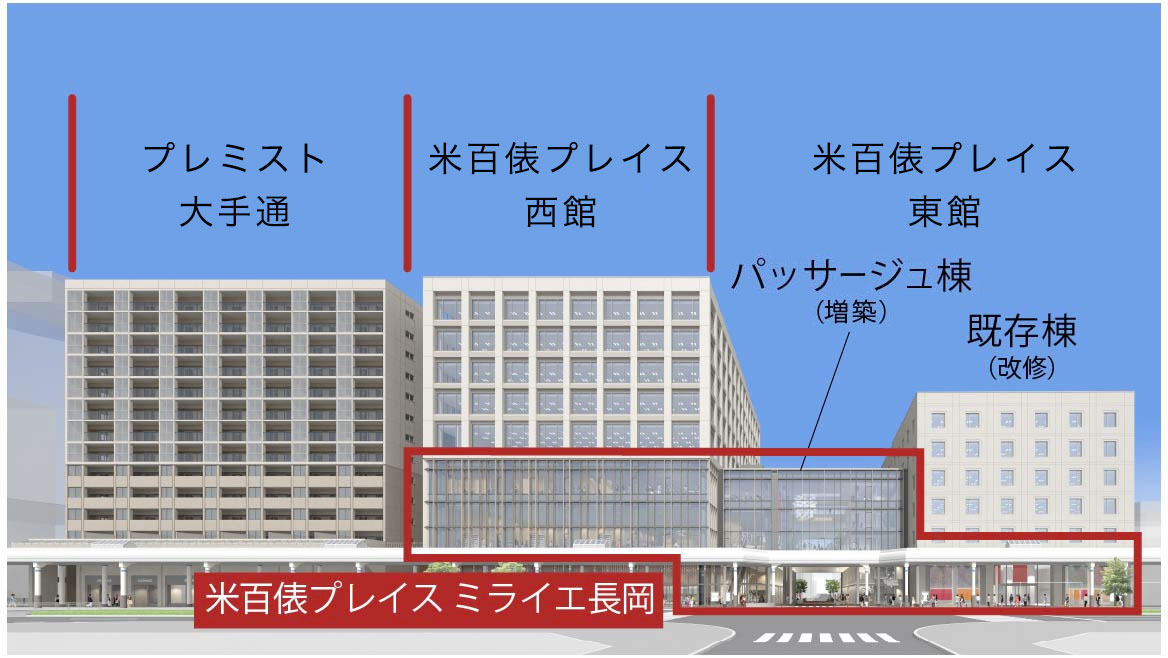
施設のご紹介
※「『米百俵プレイス ミライエ長岡』について」で使用している画像・動画は全て長岡市からの提供素材です。
3・4階イメージ 集い・憩い・学び・知るメインフロア
3-4F.jpg)
5階イメージ 起業・創業、産業支援フロア

特徴(2)米百俵プレイス東館(B街区)既存建物の有効活用
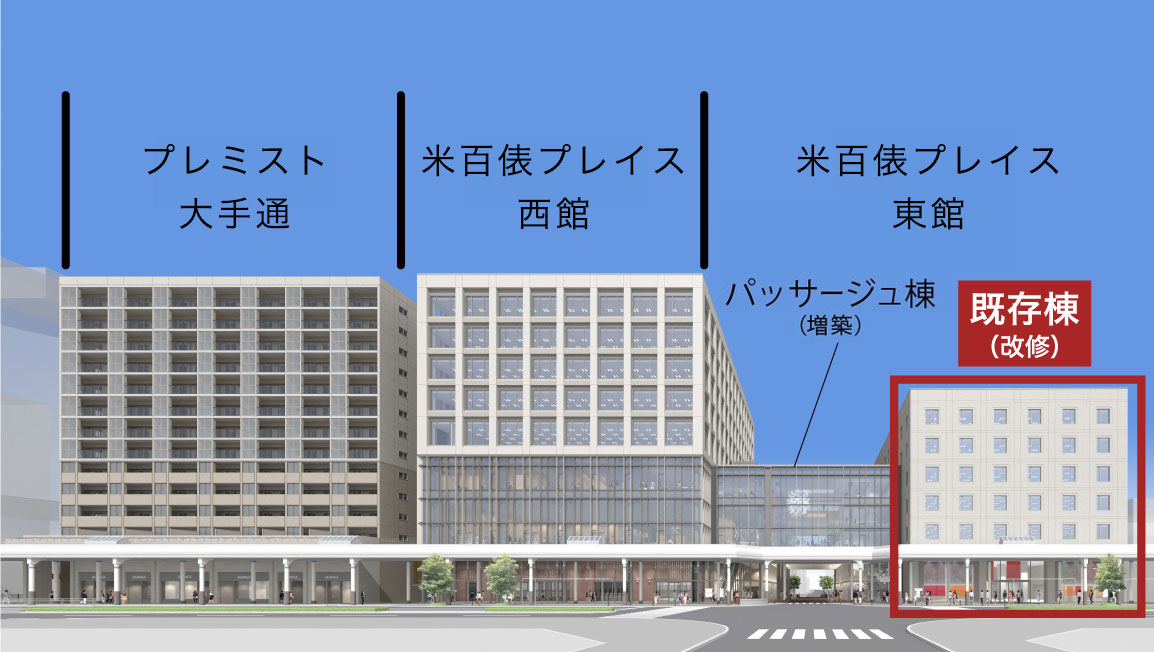
-
 東館(B街区)既存棟従前の様子
東館(B街区)既存棟従前の様子 -
 東館(B街区)既存棟竣工後(イメージ)
東館(B街区)既存棟竣工後(イメージ)
東館(B街区)の従前建物は、リノベーションを行い既存躯体を有効活用することで、工事費を縮減しています。また、地域の象徴的な建物の外観を継承することも可能になりました。
-
<既存第四北越銀行長岡本店 撤去イメージ>
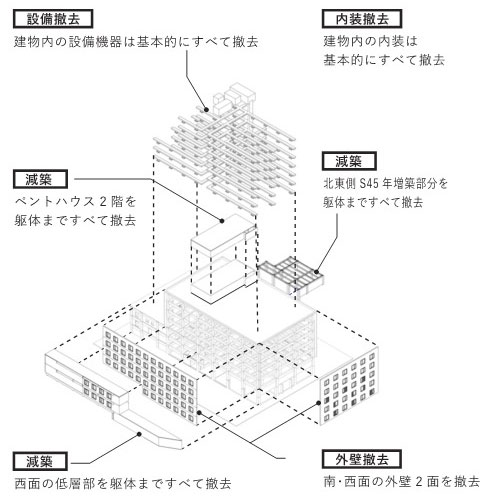 東館(B街区)従前建物撤去イメージ
東館(B街区)従前建物撤去イメージ -
<既存第四北越銀行長岡本店 改修イメージ>
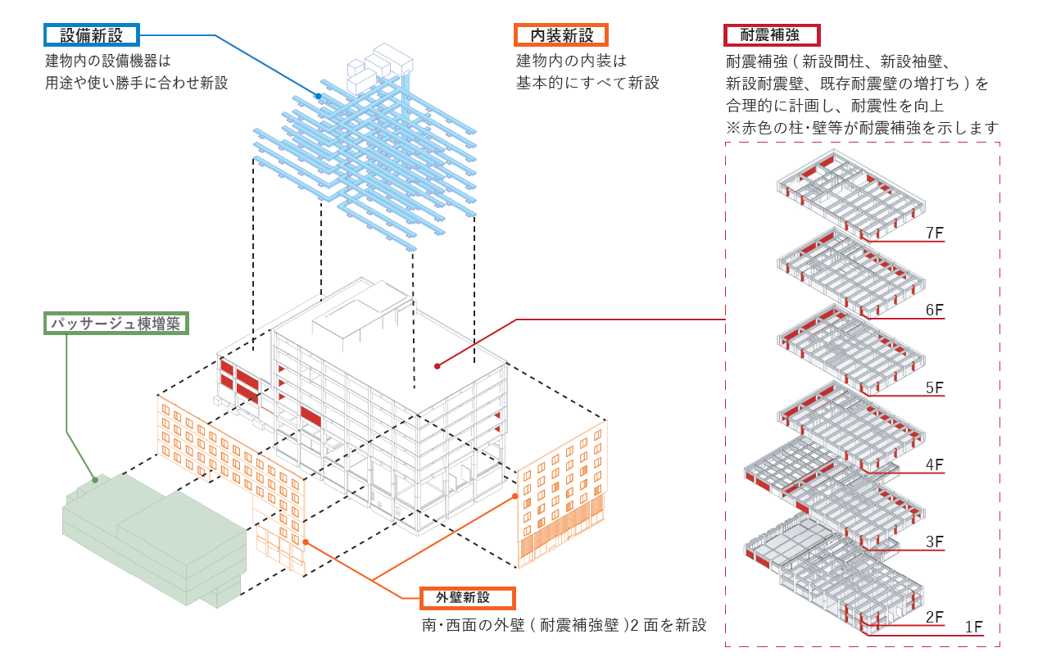 東館(B街区)従前建物改修イメージ
東館(B街区)従前建物改修イメージ
特徴(3)旧市道をイベントスペース「トオリニワ」に
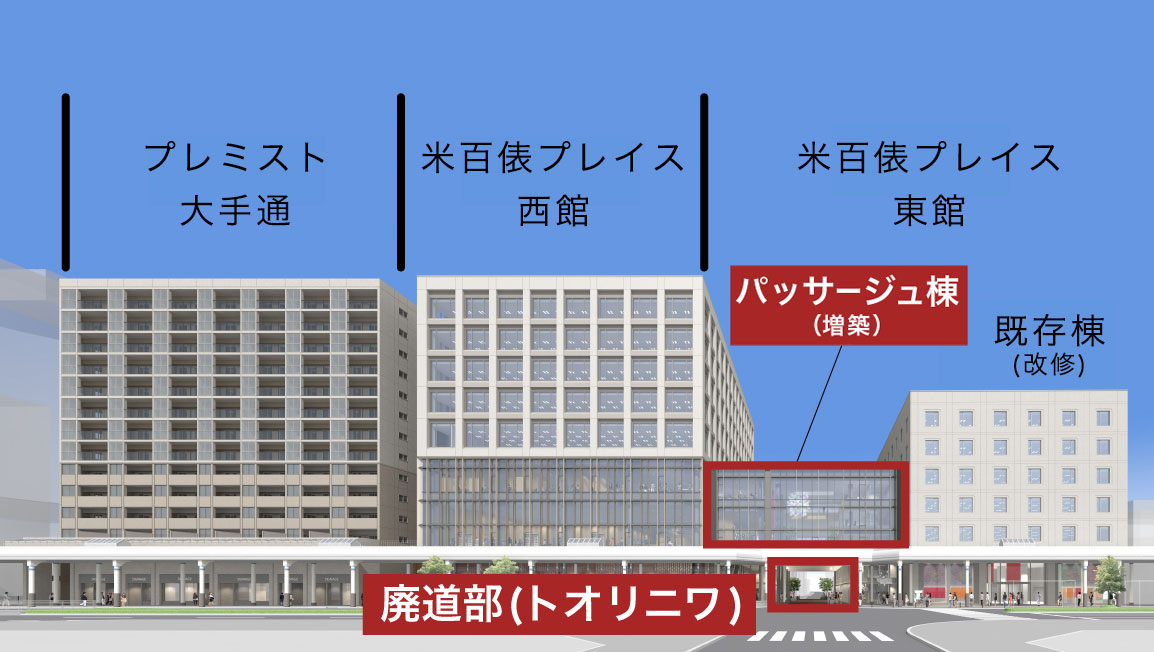
米百俵プレイス西館と東館の間を走る市道401号線は再開発事業で廃止し、東館の敷地となります。再開発事業後もコミュニティ道路として車両通行機能は維持し、イベントスペースとしても利用できる「トオリニワ」を整備します。また、上空には西館と東館を接続するパッサージュ棟が整備され、屋根のある屋外広場となります。
-
 「トオリニワ」の様子(日中)
「トオリニワ」の様子(日中) -
 「トオリニワ」の様子(夜)
「トオリニワ」の様子(夜)
 パッサージュ棟「グランパッサージュ」の様子
パッサージュ棟「グランパッサージュ」の様子
※長岡市からの提供素材です。




