~都市の景観について考える~
団地遺産からみた景観づくり
 花見川
花見川 川口芝園
川口芝園植田 実氏[住まいの図書館出版局編集長、建築評論家]

団地遺産から学ぶ、都市デザイン、集合住宅とは。
今回は、日本の編集者の中でも最も多くの住まいを見てこられた植田実氏にインタビューをお願いしました。
聞き手 UR都市機構 都市デザインチーム チームリーダー 木下 庸子
当時の公団住宅の設計とは
木下:1955年からスタートした日本住宅公団の役目は住宅供給から始まり、現在では都市再生機構とその名を変えて、都市をプロデュースする役割にシフトしています。植田さんはおそらく日本の編集者のなかで最も多くの住まいを見てこられ、都市の移り変わりも見てこられたかと思います。今日は、公団がつくってきた団地の話を中心に据えて、そのなかから都市景観を考える上でのヒントになるものをいただけたらと思っています。まず最初に、公団の印象についてお聞かせいただけますか?
植田:第一に、これだけの規模で多くの住宅を供給している公的機関は世界にも例をみないようですね。それと日本はイギリスのLLCやGLCの影響を圧倒的に受けたという先入観を僕は持っているのですが、どちらかというと、公的な住宅と民間の住宅が明確にわかれているようですね。民間による低・中所得者層の住宅建設を認可して、バックアップする仕組みでしょう。ドイツがそうですし、フランスのHLM(アッシュエルエム)もそうでしょう。その辺は国によって色々だと思いますが。
木下:住宅公団のことを知ったのはいつ頃からでしょうか?
植田:1960年代の初めの頃ですね。その頃、メディアは公団住宅について意地悪な見方もしていましたね。お墓のように同じものが延々と並んでいて自分の家がわからず、間違えて他の人の家に入ってしまってトラブルが起きた。だから、世間はいいイメージを必ずしも持っていなかったと思います。
木下:私は団地に住んでいた経験もあって、住んでいた当時は正直戸建てに住んでいる友達がうらやましかった。でも、振り返ってみると昭和30年代では、平均的な日本人の住まいとして団地が果たした役割は大きいですよね。戦後の住宅難だったわけですから、どんどん量を供給して数をこなさなければいけない時代で、内部のプランニングひとつひとつ考えてい時間はとうていなかったという背景があると思います。数をこなすための仕組みとして標準設計という手法が考えられたと思うのですが。
 植田 実氏
植田 実氏
植田:設計の視点から見れば、住戸をつくる規格ががんじがらめで、ドアのサイズやヒンジの位置、押入の棚の梁の数まで、あらゆることが決まっていたという話を、公団に関わった建築から聞いたことがあります。だから、普通の建築家がその規格をすべてクリアして公団住宅の設計するのはなかなか難しい。
木下:過去の記録を読んでみますと、「団地設計とは環境をつくることである」とはっきり書かれています。つまり、昭和30年代に団地に携わった人たちはとても真剣、熱意を込めて設計、それから計画に取り組んでいた。住戸の設計ではやれることが限られているわけですから、どこかで自分たちがつくったという痕跡を残したい。設計者のその想いが配置計画に表れていますよね。私は資料を通じてそのことに気付かされたんです。
植田:まさにそうだと思いますよ。『都市住宅』が創刊された1968年、公団がスタートした1955年頃から1960年代末までの住宅公団の設計手法をまとめたいと思っていた。膨大な量の住宅を短期的に供給しなければならなかったのですからね。だから、1960年代末までの主な設計は外部空間であり、配置などに設計の力が注がれている。
木下:今は植田さんにもご協力していただきながら都市デザインチームで過去の遺産を振り返ろうとしているところなのですが、やはりそういう精神のなかでつくられてきた団地を今一度振り返ってみて考えることは、今後の景観を考える上ですごく重要じゃないかなと思います。ちょうど植田さんも公団のまとまった資料はないよねとおっしゃっられていたし、実は私も都市デザインチームに在籍している間に何らかの形でまとめたいと思っていました。いいタイミングですよね。
 木下 庸子氏
木下 庸子氏
植田:僕もずっと、公団の人が当時言っていたそのことが頭の片隅にあったんです。主な設計対象は外部空間であったとすれば、基本的に内部は規格にのっとったスタンダードな住戸で構成されていると想像できますね。違いがあるとすれば外部空間をどのように工夫しているか。それを編年的にまとめていただいたこともあるのですが、開いた形で配置したり、やや集中型にしたり、ポイントタワーでスペースを稼ぐとか。そんなにたいしたことはできないだろうと思ってました。たいしたことないというのは失礼だけれど、資料だけでは絶対わからない。差異が微妙で、実際に見ないと区別がつかないだろうと。
まぁ、すべて見るというスタンスは一応、編集者として僕はそういうやり方をやるので……。
木下:それが怒濤の団地見学の始まりでした(笑)。私が都市デザインチームに在籍した年がちょうど機構の50周年でしたから、50ヵ所の団地を植田さんと私でピックアップしようと。そして、その50団地について何か書いてまとめようというところから話が始まったように思います。ただ、私は50団地を全部見なくてもいいかなと思っていたのですが……。植田さんは何しろ全部見ないとダメだよと(笑)。
植田:見るとは言っていたんだけどね……。おそらく10団地ぐらい見たら飽きちゃって、そのあとどうするかはそのときになって考えればいいやと(笑)。
木下:駆け足でしたが綿密なプログラムを組んで見てきました。雰囲気はつかめたと思うのですが。
植田:たいした違いはないだろうと思って見に行ったら驚かされてしまいましたよ。こんなにおもしろかったのかと。今の編集・出版状況は、今さら新しい特集は組めないというぐらい、みんなが同じ建築家や同じテーマの特集を延々と追いかけあっている過酷な競争のなかにあるのですが、そのなかで誰も忘れてしまって手をつけていない、見てもいなかったものを丸ごと見せてもらった。そのくらい感動しました。宝の山に入ったというか。
木下:植田さんのなかでも評価がガラッと変わったわけですね。
植田:先ほど悪口が多かったと言いましたが、その対象である初期の中層で、板状を中心とした団地を見て思ったことは、同じ中層板状棟にいかに命を吹き込むか。当時の公団担当者のその工夫は半端じゃなかっただろうなと。同じ住棟を使いながらそれぞれの団地に個性を与えるなんて程度ではなかった。おそらく日本人が初めて体験することになる生活環境を創造するための努力だったんじゃないか。それまでの日本の住宅地にはまったくなかったわけですから。
木下:きちんとした理屈・理由が見てとれましたよね。配置計画もしっかり考えられている。私はそのことに驚きましたし、今後のたいへんなヒントになるなと。
植田:戦前の住宅地は普通の戸建て住宅地ですよね。いわゆる大正文化住宅であり、昭和モダン住宅です。つくり方も今と同じで、それぞれの建て主が好きなスタイルで勝手に建てる。ですから、集合住宅として同潤会アパートメントが70年代ぐらいになってようやく再評価され始めた程度です。今度はそれがクローズアップされていて、逆に同潤会のものしかないみたいな固定概念に偏ってきたなかで、最初期の公団住宅はおもしろくないという評価が現在に至っているわけですね。
木下:どうしてそうなってしまったのでしょうか?
植田:その理由は実に簡単。誰も改めてきちんと見たことがなかったからですよ。公団内部の人はきっとよくご存じだったでしょうけど、自分たちがどういう手法で公団の団地をつくってきたかという計画側からの説明を外の者は聞くだけだったから、だから、実際にきちんと見ていない人にはなかなか通じない。木下さんもおっしゃられていましたけど、実際に見てから改めて資料を読んでみると、じつはすべてきちんと書いてある。
新たな生活の場としての先進性、そして独自性
木下:植田さんとこれまで50以上の団地を一緒に見て回りましたが、団地の特徴をあだ名で表現してみようとおっしゃられましたよね。
植田:あれだけ数を多く見ると覚えきれないということですね。とりあえずは道のかたち、住棟の配置、地形といったサイトプランと訪ねてみての実は実感から名づけてみようとしているわけだけれど、区別するという以上に、50の団地には、50の個性があるはずだから、それを確認したいわけですね。で、例えば「高幡台」は草刈りの“大鎌”(笑)。
木下:「市川中山」は、直角だから“スコヤ”とか“金尺”、「米本」は“米”。まさしく「米」という字の配置(笑)。でも実は、配置の妻側で囲まれた部分には年齢がちょっと高い子ども向けの、親の目が届かなくても大丈夫な児童の遊び場をしっかり設けている。ユニークなグルーピングの配置手法をとっています。“砂時計”と名付けた「金杉台」は、直角に交わる道路、歩行者用三叉路という道路計画になって
いて、化学方程式みたいでおもしろい図柄になっている。それをベースに建物を配置しています。どれも非常に理屈が通っていますよね。
植田:けっこうふざけてるよね(笑)。
木下:ユーモアがある(笑)。
 高幡台
高幡台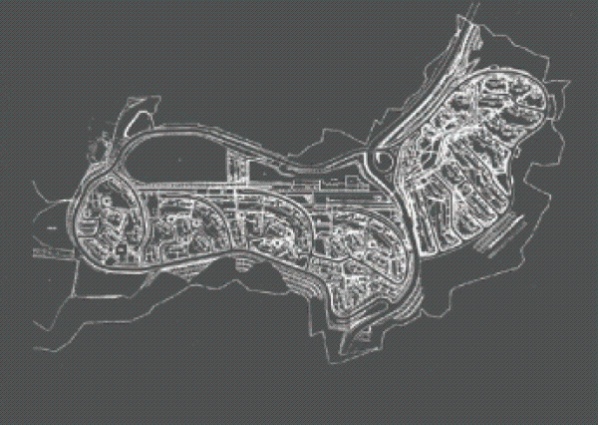 配置図
配置図 米本
米本 金杉台
金杉台 配置図
配置図植田:そういうふうに見えるということは当時の設計が高揚していたからだと思いますよ。何かこれまでにない工夫をしてやるぞという気持ちが設計者にあったからこそ、ユーモラスな、おもしろい発想にもきちんと取り組めたんじゃないかな。やるべきことがあった時代だったんですね。
木下:ノルマとして数はこなさなければいけないという時代でしたけど、そこに設計の喜びを見出していた時代だったんだなと思いました。
植田:それとやはり、生活の場ということでしょうね。店舗施設も相当大胆ですよ。むかしは下駄履きと呼んで、住棟の1階を店舗にしているだけじゃないかと軽く考えていましたけれど、実際に行って見てみると「こんなことをやっちゃうの?!」という驚きも、おもしろさもあった。ある団地には三越が入っていたほどでしたから、団地のイメージそのものも最先端で新しいものだったのでしょう。
木下:「花見川」では、当初から住んでいる女性が自慢してましたよね。引越してきたときは鼻高々だったのよと(笑)。市街地における集合住宅では下駄履き団地がありましたけど、一方、郊外では店舗施設をどこにとるかという議論が再三なされた上で計画されていることに感心してしまいました。
植田:おそらく関東大震災以降に生まれた新しい生活の器や商売は、どの時代でも都市建築の最先端なわけですよね。アパートメントという言葉自体が当時は憧れでしたし、それから美容院、クリーニング屋さん、写真スタジオ、歯科医院もそう。外国から入ってきたモダンな商売が最先端。それらとは違う形であったけれど、住宅公団の団地という言葉と新しいタウンセンターに憧れがあった。だからつい、三越も団地に店舗を構えちゃったんじゃないかな(笑)。
木下:たしか、「赤羽台」には明治屋があったと聞いた記憶があります。
植田:そうですか。当時の公団の団地が持っていたイメージはハイソで高かったはず。高級なイメージが庶民生活の基準へとだんだん変わってきた。オイルショックでトイレットペーパー騒ぎになったときの「高島平」の様子が報じられた頃かな。パニックがあるとテレビ局が行っていた、絵になるから(笑)。そうやって生活の現場を押さえるような形でメディアが団地を肯定しはじめた一方で、生活の最先端のイメージはまた既存の都市の中に埋め込まれていったわけです。それとは別の、新しい生活環境形成がいつのまにか進んでいたわけですね。最初の公団住宅は都心において、あるまとまったスペースを確保していて、都心の中の郊外という独特な風景が出てきた。陸の孤島という言葉もありますが、それは戦前の中央線沿線などの郊外住宅地とはまったく違う形で現れてきたように思います。新しい集合住宅による生活空間をつくらなければいけないという想いがあったからこそ、そのときつくられたものの密度が高いんじゃないかな。
木下:それから、30年40年が経って今見てみますと、見事なまでに樹木が成熟していますよね。
植田:僕も感動しましたよ。こんなに木が美しく育ったのかと。それはオープンスペースを重要視した団地でなければ絶対ありえない出来事でしょうね。大きなスケールでまとまった自然ですから、いい感じですっと残っている。今の日本の住宅の庭にはどうしても限界がありますから、これからは戸建て住宅の自然との格差がますます出てくる気がします。
木下:建物がその背景になっていて、それだけで景観、風景になっている。素晴らしいことだと思います。
裏返せば、見えてきたものがある時代
木下:公団はさらに、いわゆるLDK型という住戸のプランの定型が確立してからは部品開発に力を注いだわけですが、その点においても果たした役割は大きいと思います。キッチンの開発もしてきたわけですし、バランス釜にしろ、自分の家にお風呂があることがすごくありがたい時代でしたよね。私も最初は社宅住まいで共同風呂でしたから、小さい頃に移り住んだ阿佐ヶ谷団地にはお風呂とトイレが付いていて、そのありがたさを子どもながらに実感した思い出があります。さらに、海外なら公開しないであろうディテールも公開していて、私たちが設計事務所に勤めた頃は公団のディテール集はまさに設計者にとっての参考書のようなものでした。みんなが机の脇にそのディテール集を置いて参考にしていましたから。ただ、公団はそうやって開発においてもリードしてきたわけですけれども、やがて他のメーカーが追いついて、さらに開発が進んでしまった。昔の
人がすごく苦労して築きあげてきたものが、ある段階以降、完成形となってしまったのかなと思うのですが、植田さんはどうお考えでしょうか?
植田:部品開発に限らず、団地の住戸についても言えますよね。その修正の時代があったように思いますが。
木下:そのように位置づけたほうがいいのでしょうか?
植田:普通の住戸ではもはや受け入れられないからと、不整形な部屋やプラス・アルファの部屋をつくったり、ロフトのような収納をつくったり。収納量はバツグンだけれど天井高が極端に低いとか……。そういう工夫には楽しさよりもどこか奇嬌な感じが出てしまって、なかなか難しいものですね(笑)。ただ、おそらくは公団内部も気付いていたんでしょうね。これはまずいなと。そういった手探りの時期はどうしてもあいだに挟まれている。それから、中層板状棟が長大な住棟形式になっていき、ついには東雲のような思い切った企画に至る流れもありますね。
木下:そういえばつい先日、「川口芝園」の団地づくりに関わられた人にお会いして話す機会がありました。周辺の街並みからして大きな住棟をつくるような整備はなされていませんから、道が細すぎてコンクリートを車では搬入できなかったそうです。結局、団地脇の鉄道でコンクリートを現場まで運んだそうです。そういう話を聞くと、本当にいろいろと挑戦したんだなということが身に染みてわかりますね。あの団地には“スーパー屏風”というあだ名を私は付けたのですが。
植田:たしかにあの団地は、木下さんがおっしゃられたように屏風のように延々と続いて建っていますよね。大友克洋さんが1983年に発表したSF漫画『童夢』の舞台となった団地に似ていて、それについては以前別の原稿で書いたことがあるのですが、団地内で超能力者同士の戦いが起きて窓ガラスが割れたり、住戸のガス栓が超能力で開けられて一斉にガス爆発するシーンがあったりする。ストーリーは惨憺たる状態が描かれているのですが、あのような集合住宅が持っている一面をうまく書いている。要するに、ものすごく大きなスケールになると避けられない圧迫感みたいなものがあるわけだけれど、それも思い込みかもしれない。「大島」や「奈良北」の一見画一的な巨大さや一見過剰な長大さにはむしろ解放感がありましたから。大きさの持っている不思議さというのか。
木下:大きなスケールの中では人の存在がアノニマスになる。無名性とでもいうのでしょうか。
植田:Eメールにも似ていますよね。それは、タイル張りで一部表情を変えてみたり、部分的にちょっと変わった形を組み込んだりという程度の、つまりデザインだけで処理できることではないと思います。ただ、裏を返せばそういういろいろなことが今は見えてきたわけですから、これからはすごくおもしろい時代になってくるはずですよ。
集合住宅の保存とこれから
木下:昭和30年代に、家族のためにどのような住まいがいいのかを根源から考えたことと同じように、現在の多様化する家族に求められている多様な住まいはどういうものなのか。東雲のさらに上を目指して徹底的にもう一度考える必要があるように私は思っているのですが、ただその一方で、公団の事業は77万戸もの住戸の管理と古い団地を建て替えていくだけでもやらなければいけないことがたくさん残っています。私は個人的に、昭和30年代の団地が姿を消していくのかと思うとすごく残念だなと思ってしまうのですが……。
植田:やはり集合住宅の宿命というのは、デザインの良し悪しを超えた本来の性格としてはモニュメントにはなりえないわけですよ。住むための建築というのしまう、住み込むべきものを「建築」に切り替えて残すわけですから。特殊な例なら割り切って残せるかもしれませんけど、公団の場合は戦後の大変な時代を供給することで展開してきたわけですから、その一部をどう残すかは本当に難しい。それこそ、これからの問題ですよね。それと、公団の仕事が商売に近くなってしまうとしたら、ますます消費型のデザインになっていく。住む器というのは思った以上に単純になりうるわけですから。それを超えたもっと大きなテーマつまり最初期に掲げた生活環境創出に立ち向かっていれば、絶対にすごいものができるんじゃないかな。木下さんがいわれた初期
の団地が消えていくことの残念さは僕もまったく同感ですが、同潤会アパートメントも公団住宅も、建築というのは写真や図面や調査記録だけではけっして残せない。記録するには建築そのものを残すのが、一番効率がいいんです。建築そのものなら、時間も加わって、専門家だけじゃなく一般の人にも容易に読める。いわば環境についての大きな本だからですね。50年間の遺産を何らかの形で活かす可能性があるとしたら、それは現在の機構にしかできませんよ。世界のどこにもない組織なのですから。
※本インタビューは木下庸子氏が在職期間中に行われたものです。




