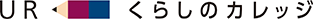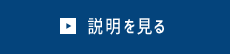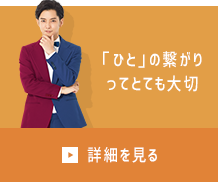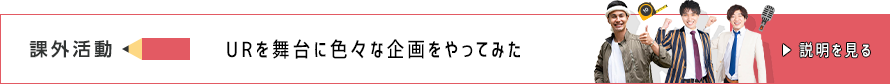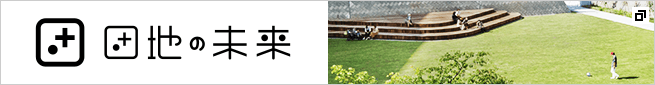住みたいへやの選び方
団地とマンションの違いは?団地に住むメリット・デメリット

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります
団地とマンション、それぞれをイメージはできても、違いを明確に定義できる人は少ないでしょう。区別するポイントは、団地は同じ敷地内に複数の住棟が建てられているということ。緑地や広場、住居以外の施設が併設されている場合もあります。現在は、公的機関や地方自治体などが管理・運営する集合住宅を、団地と呼ぶことが多いようです。ここでは団地暮らしの魅力、メリット・デメリットを解説。おすすめの団地も紹介します。
団地とは?マンション・アパートとの違い
団地、マンションのほかにも、アパートなど集合住宅にはさまざまな名称があります。それぞれの言葉の意味や、定義を確認するところから始めましょう。
●団地の定義とは?
「団地」を辞書で調べると「同じ機能を持つ建物や関連する施設をまとめて、集団的に開発された一団の土地のこと」とあります。工場のある「工業団地」、倉庫のある「流通団地」などの用語と同様に「住宅団地」という言葉があることが分かります。住宅団地には「同一敷地内に二棟以上」、「50戸以上の住戸」といった定義があるようです。複数の住棟が計画的に配置され、道路や公園、さらには商業店舗や教育施設などと一緒に整備されたケースも少なくありません。一戸建ての住宅地も、住宅団地に含まれることがあります。
住宅団地を省略して団地と呼ぶようになったといわれますが、「集団住宅地」という言葉がルーツだという説もあります。実は、法律で団地の詳細な定義がないこともあり、民間の大規模なマンションも団地といえなくもありません。しかし今は、日本の高度成長期から都市部を中心とした住宅不足に対応して建てられてきた、公的機関や地方自治体などが管理・運営する集合住宅について団地と呼ぶのが一般的でしょう。
マンション、アパート、団地については、構造的な特徴で区別できるところもあれば、違いが分かりにくいところもあります。この三つについては集合住宅という総称が一般的に使われていますが、法律上は「共同住宅」と「長屋住宅」に分けることができます。エントランスや階段、廊下など、住民同士で一緒に利用する“共用部分”のある住宅が「共同住宅」、“共用部分”がなく外から直接出入りできる住宅が「長屋住宅」となります。
この区分に従うと、団地とマンションは共同住宅がほとんどですが、アパートの一部に長屋住宅がありそうです。テラスハウスと呼ばれるタイプは、共同住宅のように思えますが長屋住宅となります。以上から分かるように、建物形態や法律上の区別ではなく、不動産業界の慣例で名称を使い分けているケースが少なくありません。
つまり、マンション、アパート、団地、それぞれの名称の使い分けについては、法律などで明確に定義しきれていないところがあります。最近建てられた団地の中には、一見するとマンションとの違いがないように思える建物もあるかもしれません。次項で解説するポイントを参照することで、物件選びなどの助けになるでしょう。

●マンション・アパートとの違い
- ・マンション
- 3階建て以上の鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の大規模な集合住宅をマンションと呼ぶのが一般的です。民間の不動産会社やデベロッパー、土地オーナーなどが主体となって建築を計画し、建物完成後に各住戸を販売する「分譲マンション」と、各住戸を貸し出す「賃貸マンション」があります。建物の構造や間取り、設備仕様により、価格も家賃もさまざまです。しかし、分譲も賃貸も採算性が重視されるのは共通です。そのため、敷地を最大限活用するケースが多く、広場や庭などが併設されることは少ないでしょう。
- ・アパート
- 2階建て以下の木造や軽量鉄骨造の小規模な集合住宅をアパートと呼ぶのが一般的です。マンションと比べると敷地面積が狭く、建物が小さめになるため住戸も少なくなり、居住面積や間取りもコンパクトな物件が主となります。階段や廊下が外に面していることが多く、エレベーターがないなど、共用施設が少なめの傾向があります。家賃が比較的低めに抑えられることから、学生や一人暮らし向けの物件が多いかもしれません。
- ・団地
- 戦後の高度経済成長期に、都市部を中心とした人口増加で住宅不足が発生し、公的機関や地方自治体により多くの住宅が建設されてきました。中堅所得者・勤労者向けの住宅を日本住宅公団[現在の独立行政法人都市再生機構(UR)]と住宅供給公社が担い、住宅に困窮している方などが対象の住宅を都道府県や市区町村が整備してきました。民間の事業者ではない、この3種類の管理・運営主体による集合住宅を、一般的に団地と呼ぶことが多いでしょう。
- 独立行政法人都市再生機構(UR)の「UR賃貸住宅」、住宅供給公社の「公社住宅」、地方自治体の「公営住宅(県営・市営住宅など)」があり、現在の団地は賃貸集合住宅が主になっています。ほとんどが鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造で建てられています。建物形態や間取りはさまざまですが、複数の住棟があり戸数が多く、敷地内や周辺の全体計画に基づき緑地や公園、商店や学校などが整備されていることもあります。
団地に住むメリット・デメリット
団地なら、築年数やエリアによっては手ごろな家賃で、部屋が広く暮らしやすい環境の物件が見つかるかもしれません。ただし、間取りや設備が古いときは工夫が必要でしょう。
●団地に住むメリット
前述の公的機関や地方自治体などが管理・運営する団地は、初期費用や家賃・管理費などを抑えやすいといえるでしょう。入居時の礼金や仲介手数料、さらに更新料などが無料だったり、入居後の家賃を節約できる制度があったりします。もちろん、物件の間取りや床面積、築年数、立地などの条件により家賃は変わりますが、団地なら賃貸マンションに比べて住居費を抑えた暮らしがしやすいかもしれません。
多くの団地は良好な住環境を実現できるよう、建物同士の間隔が十分に確保され、ゆったりとした敷地設計になっています。室内に太陽の光や、自然の風を取り込みやすく、バルコニーが南面して日当たりが良ければ洗濯物が乾くのも早くなります。日中の暖房効率も良くなるためエアコンの使用頻度を減らせるかもしれません。
頑丈な鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造で建てられていることが多いので、安心して暮らせるのも団地のメリット。築年数が経過しているレトロな佇まいの物件でも、耐震診断・耐震改修や、計画的な修繕が進められているケースが多いようです。
団地は地区の全体計画に基づき総合的に開発されたケースも多く、郊外には広場や公園を併設したものが少なくありません。歩道と車道を分離した設計が採用されている団地では、交通事故を心配せずに済みます。住棟の数が多い大規模な団地では、幼稚園や保育園、小学校、中学校、医療機関、スーパーマーケットなどが建物内や近隣にひと通りそろっていることもあります。生活しやすい便利な環境が整っていることも魅力です。

地域のお祭りや盆踊り大会、餅つきなどのイベントが開かれている団地もあります。それらは団地の自治会によって運営されていることが多いでしょう。防犯や防災などの問題についても、集会を開いて相談しながら居住者同士が協力して活動しているようです。昨今少なくなりつつあるご近所の付き合いがあり、いざというときに助け合える、緩やかなコミュニティがあるのも団地の特長かもしれません。
●団地に住むデメリット
築年数の経過している団地では、ふすまで仕切られた和室のある物件が多くあります。物件によっては洗濯機置き場がなく、トイレに温水洗浄便座が付いていないなど、間取りや設備に不便を感じることもあるかもしれません。古くても快適に暮らせるよう、賃貸で許される範囲のDIYで工夫できると良いでしょう。現代の生活スタイルに合わせて畳をフローリングにしたり、水まわり設備を入れ替えたりした、リノベーション済みの物件も増えているようです。
共有施設が充実している民間マンションと違って、5階建て以下の団地にはエレベーターが設置されていないこともあります。大きな家具や家電を移動するときは方法を考える必要があるかもしれません。オートロックや宅配ボックスなどが備わっていないケースも多いでしょう。防犯カメラなどのセキュリティーが導入されている団地も限られてきます。気になる人は、物件選びや内見の際にきちんとチェックするようにしましょう。
団地は住民の高齢化が進んでいたり、人付き合いが煩わしかったりするのでは。そう考える人もいるでしょう。実際にそういった部分はあるかもしれません。ただ、若い子育て家族の中には、高齢者が多いことで日中の時間帯に子供が見守られている安心感や、お祭りなどで年代の異なる人と交流できることに、良さを感じる人もいるようです。リノベーションした部屋に若い世代が入居し、活性化が進んだ団地も増えていると聞きます。
●団地はこんな人におすすめ
お伝えしたように、団地なら初期費用や家賃を抑えながら、部屋数が多めの間取りで床面積が広めの物件に、ゆったりと暮らすことも可能です。和室のある間取りが多いことで、押入れという大容量の収納を使って室内に置くものを減らし、空間をより有効に活用できます。趣味などにお金を使いたいので住居費を減らしたい、リモートワークに集中できる専用部屋のある間取りで暮らしたい、そんな目的を持った人におすすめです。
また、敷地に余裕を持って建物が配置されているため、日当たりや風通しに優れています。公園や広場、子供のプレイロットのほか、郊外の大規模な団地には遊歩道が設けられていることもあります。室内が快適なだけでなく、屋外で自然を感じて過ごせるのは団地ならではでしょう。子供を元気にのびのび育てたい、環境の良い郊外で自然を感じて暮らしたい、人とのつながりを大切にしたい、そう考える人にぴったりかもしれません。
リノベ物件も豊富なUR賃貸住宅
団地のメリットを生かして暮らしたい。そんな人におすすめなのがUR賃貸住宅。リノベーション済み物件や、DIYが可能な物件もあり、多様な住まいを選べるのが魅力です。

●UR賃貸住宅(旧公団住宅)ってどんな団地?
独立行政法人都市再生機構(UR)の前身である日本住宅公団が設立されたのは1955年。食事のときも、寝るときも、同じ部屋で家族が暮らす“食寝一体”が普通だった当時、ダイニング・キッチンのある“食寝分離”の間取りや、水洗トイレ、風呂、バルコニーを備えたかつての「公団住宅」はあこがれの的でした。長年にわたり時代に合った住宅を手掛けてきたことで、多様なライフスタイルや居住ニーズに応えられるのが強みとなっています。
現在、独立行政法人都市再生機構(UR)が管理するUR賃貸住宅は全国に約70万戸。都市部の高層型の住宅から、自然が豊かな郊外に広がる集合住宅まで、比較的ゆとりのある多彩なタイプの部屋がそろっていて、収納スペースもしっかり確保されています。一人暮らしに人気の1Rや1DKから、二人暮らしにぴったりな2DKや1LDK、さらにファミリータイプの2LDKや3DK、3LDKなど、暮らしに合わせて希望する住まいを見つけやすいといえるでしょう。
また、建物のほとんどが鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造で建てられ、築年数が経過しているレトロな佇まいの物件でも、適切な管理や計画的な修繕が行われています。耐震対応工事やエレベーター設置工事が進められているほか、建て替えやリノベーションが行われている物件もあり、安心して快適に暮らせるのが特長の一つとなっています。
●UR賃貸住宅のリノベーション
UR賃貸住宅には、団地の良さを生かしながら、現代のライフスタイルに合うようリノベーションした物件が多数用意されています。建物の改修などのほか、間取りや収納に大幅に手を入れたり、和室を洋室へ変更したり、水まわりの設備を新しくすることで、快適性を高めています。コンセプチュアルなリノベーションにより、洗練されたインテリアコーディネートも可能で、おしゃれな部屋に興味がある人にもおすすめです。
その一例が無印良品とのコラボレーション【MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクト】です。構造部分はできるだけ変えずに残しながら、暮らし方に応じて組み合わせができるキッチンなどを採用することで、自分の好みやスタイルで自由にアレンジできるのが特長。団地のコンパクトで風通しの良い間取りを効果的に生かし、シンプルにまとめられた内装と使い勝手の良い空間は、和・洋どちらのインテリアにもフィットするでしょう。

●UR賃貸住宅なら自らリフォーム可能な住戸も
UR賃貸住宅には本格的なDIYが可能な「DIY住宅」もあります。この物件では一般的な賃貸住宅で必要となる広い範囲の「原状回復義務」が免除になるのが特長です。契約時に3カ月間の使用貸借契約(家賃無料)と、使用貸借契約満了日の翌日を入居開始とする賃貸借契約を同時に締結することで、入居までの3カ月間は家賃を気にすることなく、マイペースでプランニングと施工を行えます(ただし、共益費のみこの期間も負担が発生します)。
「DIY住宅」以外でも、「模様替え等承諾申請書」を提出して承認を受けることで、退去時の「原状回復義務」が免除されるケースがあります。必要な手続きを踏むことで、ライフスタイルの変化に合わせて畳をフローリングに変えたり、壁紙を貼り替えたりすることも可能です。「自分好みのお部屋にしたい」、「お気に入りの家具とインテリアに囲まれて暮らしたい」という人は自分に合ったリフォームを楽しめます。
●若い世代にうれしい!お得な家賃プランが豊富
UR賃貸住宅は、礼金・仲介手数料・更新料・保証人がすべて不要(保証会社への加入も不要なので保証料も不要)。契約時に必要なお金は、敷金(月額家賃の2カ月分)と、入居月(入居日から当月末まで)の日割り家賃、日割り共益費のみ。そのため入居時の初期費用を大幅に抑えることが可能です。さらに家賃を節約できる「お得な家賃プラン」も複数用意されています。以下の項目で条件を満たしている場合は、活用してみてはいかがでしょうか。
- <そのママ割>

- 3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は妊娠中を含め、現に同居する満18歳未満の子供(孫、甥、姪なども可)を扶養し、同居している世帯です。
※3年間の定期借家契約
- <子育て割>

- 新婚世帯は最長3年間、子育て世帯は最長6年間、新婚世帯から子育て世帯へ切り替えた場合に最長9年間、家賃の最大20%(所得に応じた減額となります。上限2万5000円)がサポートされます。対象は結婚5年以内の新婚世帯、または18歳未満の子供を扶養し、同居している世帯。いずれも所得合計が月25.9万円以下の場合となります。

- <U35割>

- 3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は契約者が35歳以下の世帯。学生、単身、夫婦、子育て世帯も対象です。なお配偶者以外の同居者には一定の条件があります。
※3年間の定期借家契約
- <近居割>

- 募集家賃から5年間、5%減額されます。対象となるのは同じUR内、もしくは半径2km以内の別々のURで、親世帯・子世帯の二世帯が近居する場合で、新たに契約した世帯の家賃が減額されます。また、二世帯同時に契約する場合は、両世帯とも減額されます。条件を満たした子育て世帯については、最長5年間、家賃の20%(上限4万円)がサポートされます。ただし、世帯の所得合計が月25.9万円以下で、対象が一部団地となるなどの条件があります。
- <近居割WIDE>

- 募集家賃から5年間、5%減額されます。対象となるのは近居割WIDEエリア内のURとUR以外の住宅です。親世帯・子世帯の二世帯が近居する場合で、新たにUR賃貸住宅を契約した世帯の家賃が減額されます。近居割WIDEは、地域医療福祉拠点化に取り組んでいる物件を中心に導入されています。条件を満たした子育て世帯については、最長5年間、家賃の20%(上限4万円)がサポートされます。ただし、世帯の所得合計が月25.9万円以下で、対象が一部団地となるなどの条件があります。
シンプルで快適な暮らしには団地がぴったり
お伝えしたように、大規模に開発された団地には、広い敷地を生かして複数の住棟と広場や緑地がバランスよく配置され、生活に必要な商業施設や教育施設などが備わった物件も少なくありません。そこには、人間が快適に暮らせる住まいと環境の関係について、全体のプランがきちんと描かれていたことが分かります。ある意味ぜいたくな要素が含まれているのは団地ならではかもしれません。
築年数の経過している団地には、最新機能を備えた設備や、流行の間取りはないかもしれません。しかし、安心して暮らせる建物性能や、採光や通風が良く過ごしやすい部屋など、基本的な生活の質では高いレベルの物件がたくさんあります。また、築年数が経過していることで比較的手ごろな家賃で、部屋数が多めの広い物件に入居できることもあります。賃貸でも可能な範囲のDIYで、シンプルな室内を自分らしいスタイルで楽しんではいかがでしょうか。
UR賃貸住宅なら、水まわり設備などがリノベーションされた物件や、自分好みにDIYが可能な物件もあり、団地を検討する際の選択肢が豊富に用意されています。また、物件数が多いことで家族構成や暮らしに合わせて希望の住まいを探せます。UR賃貸住宅のHPでは、エリア、家賃、間取り、最寄り駅からの所要時間、築年数など、細かく条件を設定して物件の検索が可能です。ぜひ気軽に試してみることをおすすめします。
監修/加藤 哲哉

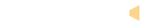
住居費を抑えてゆとりを感じる部屋で暮らせる!団地のメリットを生かそう
- ・敷地内に公園や緑地があり、日当たりや風通しの良い、部屋数が多めの間取りで暮らせて、しかも住居費を抑えられるのが団地の魅力
- ・そういった物件は築年数が経過していることが多く、必要なリノベーションがされているか、賃貸で可能なDIYで工夫して暮らせるかチェックしよう
- ・UR賃貸住宅は物件数が多く、リノベーション済み物件もあり、希望に合った住まいを見つけやすい
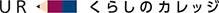
くらしのカレッジ編集部は、「くらし」に関するさまざまなヒントをお届けすることを目的に、インテリア、リノベーション、DIY、子育て、イベント情報など、生活を豊かにするアイデアや日常的に楽しめるコンテンツをご紹介しています。
お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります