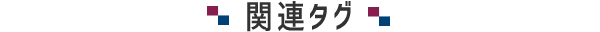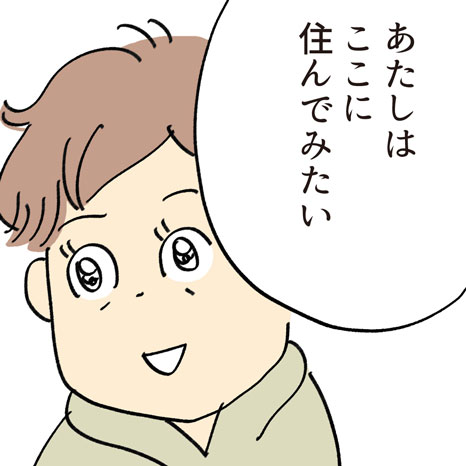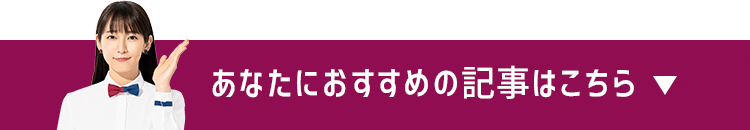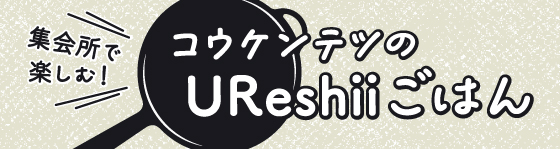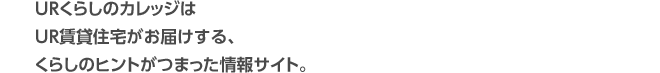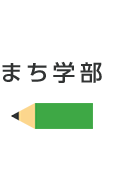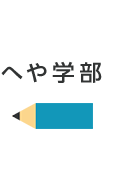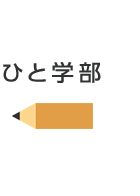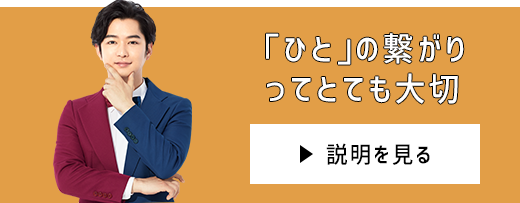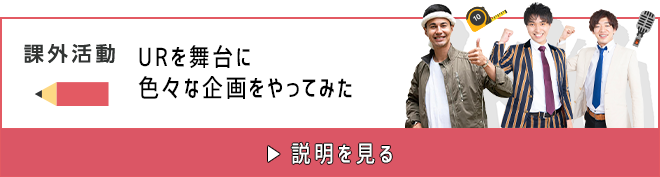住みたいまちの選び方
ユージのぶらり団地レポート【URまちとくらしのミュージアム編(前編)】

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります
タレントのユージさんがURの団地内をぶらりとお散歩する連載企画。今回は特別編として「URまちとくらしのミュージアム」(東京都北区)を見学! これまで、たくさんのUR団地をぶらりしてきたユージさんが、都市型集合住宅の歴史をたどります。案内してくれたのは、UR都市機構の野口さんです。
集合住宅の過去・現在・未来を知ろう

今回やって来たのは、「URまちとくらしのミュージアム」。ここは、旧赤羽台団地の跡地に造られた新しい施設なんですよね。
はい、旧赤羽台団地の歴史ある住棟も残していますが、集合住宅の過去・現在・未来を知ることができる施設となっています。2023年9月にオープンして、まだ屋外エリアは進化中ですが、一般の方も見学いただけるようになっているんですよ。では、さっそく「ミュージアム棟」からご案内します。
「ミュージアム棟」には集合住宅の復元住戸があるんですよね。
よろしくお願いします!

ミュージアム棟の見学は、予約制ですか?
入場は無料なのですが完全予約制で、月・火・木・金・土曜に1日3回ガイド付きのツアーで見学できるようになっています。オープン以来、ご好評いただいていて土曜日の予約は早く埋まってしまうことが多いですね。
無料でガイド付きってぜいたくですね!

ガイドツアーは各20名まで。ロビーに集合し、展示スペースに入る前に靴の上からシューズカバーを履く。
あ、この縫いぐるみは「カモちゃんず」じゃない?

「カモちゃんず」は、住宅・都市整備公団時代のマスコット。ユージさんは大阪の「中宮第3団地」で出会っていた。
「給水塔の上の方に描かれてたよね」とユージさん。
それでは、まず「URシアター」で日本の集合住宅の変遷をご覧ください。
壁と床4面がスクリーンになってるんですね!

約7分の映像で、「人は集まり、住む。」をテーマに、URがどのように集合住宅をつくってきたかをご紹介しています。
すごい迫力! この映像は引き込まれるなぁ。
映像の中でも触れていましたが、日本で本格的な鉄筋コンクリート造りの集合住宅が供給され始めたのが、1923年の関東大震災後の復興住宅でした。震災によって、42万戸もの住宅が失われたそうです。
それで、たくさんの住宅が必要になったんですね。
はい。住まいの復興として設立されたのが「同潤会」という組織です。それでは、4階に上がって「同潤会」が供給した集合住宅の復元展示を見学しましょう!
関東大震災をきっかけにつくられた集合住宅

「同潤会」は関東大震災の義援金で設立された組織で、東京都内と横浜に計16カ所の「同潤会アパート」が建てられました。
表参道にあった「同潤会青山アパート」は覚えてます! そこで映画の撮影もしたことあるんですよ。今の感覚でも、すごくおしゃれな建物でしたよね。
ここに展示されているレリーフや手すりも、デザインが凝ってるなぁ。
このころ、ヨーロッパでは近代建築が盛り上がっていたんですね。大量の住宅を供給するという使命ではあったのですが、同時にヨーロッパ的なテイストも意識していたようです。
集合住宅のような大きな建物は街のデザインにも影響しますもんね!

もう一つ、注目していただきたいのが建物の配置です。「清砂通りアパート」ですが、ロの字形になっていて中庭がありますよね。これは住民のコミュニティの場として設計されていたんです。
へー! 今のUR団地に広場や集会所があるのと同じ考え方ですね!
おっしゃる通り、集合住宅のつくり方として今に生かされているんです!
それでは、1927年に完成した「同潤会代官山アパート」の復元住戸を見てみましょう。

単身者向けの部屋は廊下付きで復元されている。
「このガラス、ゆがみがあるから当時のものですね!」とユージさん。

ここが単身者向けの住戸。今でいうワンルームですね。
これ、ベッド!?
はい、作り付けのベッドで下は収納スペースになっています。コンパクトな部屋ですが、よく考えて設計されているのが分かります。
キッチンはないけど食堂で食事できるし、お風呂やトイレは共用なんですね。
面白いなぁ、当時の暮らしが想像できますね。
次は、時代が一気に進みまして、1957年に竣工した「蓮根団地」の復元住戸に参りましょう! 整備したのは1955年に設立されたURの前身「日本住宅公団」です。

ダイニングテーブルだ! これも備え付けですか?
はい、まだいすに座って食事をするという生活スタイルが浸透していないこともあり、備え付けでした。このころ、食べる部屋と寝る部屋を分ける「食寝分離」という考え方が提唱され、「蓮根団地」ではダイニングキッチンが標準設計になりました。

「ダイニングキッチンはテーブルが近くて良いよね。家事がずいぶんと楽になっただろうなぁ」とユージさん。
つまり、「蓮根団地」は「2DK」という間取りの先駆けだったんです。
集合住宅はいつの時代も最先端の暮らしを提案していたんですね!
進化する集合住宅はあこがれの住まいへ

次は、1958年竣工の「晴海高層アパート」です。このころは都心に人口が集中してきて、建物が高層化していきました。「晴海高層アパート」は前川國男さんが設計した10階建てのスキップアクセス方式でした。
スキップアクセス方式、というのは?
こちらの案内図をご覧ください。これは実際に使われていた案内図で、「晴海高層アパート」内の地図のようになっています。

あ、エレベーターが各階に止まらないんですね?
そうなんです。エレベーターが停止するのは1・3・6・9階で、停止しない階には廊下もありません。つまり、5階に住んでいる人は6階でエレベーターを降りて廊下を通り、階段を降りて5階の部屋へ。

エレベーターも復元。当時はエレベーターガールがいて、ボタンの操作をしていたそう。

エレベーターのボタンは、1・3・6・9のみ。
なるほど~。初めて来たお客さんは迷っちゃいますね(笑)。でも、廊下がない階は部屋を広くできたってことですよね!
そうなんです。また、暮らしていくうちに家族構成や生活スタイルが変化することを踏まえ、2戸の住戸をつなげて1戸にできるようにする工夫も見られます。今から、廊下がない階の復元住戸を見てみましょう。

階段を降りてやってきました。ここが廊下のない階。確かに、広々してる!
廊下がある階の部屋より約9平方メートル広いんです。また、「晴海高層アパート」ではステンレス流し台が採用されています。プレス加工による量産化が可能となり、団地の供給とともに普及していきました。
設備も充実していたんですね。晴海なら海も見えただろうし、人気のデザイナーズ物件だったんですね。
今回紹介した団地のほかにも復元住戸や展示スペースはたくさん!
住戸以外にも、インターホンやドアノブなどの住宅部品を壁一面に展示した「団地はじめてモノ語り」のコーナーも必見。

【まとめ】集合住宅はいつの時代も最先端!

「URまちとくらしのミュージアム」のミュージアム棟、満喫しました! どの復元住戸も興味深かったなぁ。集合住宅が最先端の暮らしを提案してきたから、そのままライフスタイルの歴史になっているんだね。
「同潤会アパート」が建てられたころに「コミュニティ形成の場」という考え方ができたことにも驚きました。
後編では、屋外スペースと「ヌーヴェル赤羽台」をぶらりするよ!
- ユージの「いいね!」in URまちとくらしのミュージアム

ユージさんが「晴海高層アパート」の模型を撮影。
「この円柱形のものは何だろう?」正解は、後編にて!

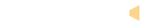
集合住宅の歴史はライフスタイルの歴史そのもの!
- ・「URまちとくらしのミュージアム」は復元住戸の見学ができ、集合住宅の変化を知ることができる人気スポット
- ・関東大震災をきっかけに設立された「同潤会」が集合住宅の基礎を築いた
- ・時代の進化に合わせて変化した集合住宅
URまちとくらしのミュージアム
東京都北区赤羽台1丁目4-50
2023年9月15日にオープンした、URの企業ミュージアム。都市のくらしの歴史を学び、未来を志向する情報発信施設。
見学施設「ミュージアム棟」は、一般の方も完全予約制(入場無料)で来館できます。

「おしゃれなごみ箱が欲しい!」、「食材をすっきり収納したい!」みなさまから寄せられたご要望やお悩みに応えるべく、タレントのユージさんがゲストを迎えてプチDIY対決!「プチDIYでくらし快適化」わかりやすい動画つきで紹介中!

くらしのカレッジ編集部は、「くらし」に関するさまざまなヒントをお届けすることを目的に、インテリア、リノベーション、DIY、子育て、イベント情報など、生活を豊かにするアイデアや日常的に楽しめるコンテンツをご紹介しています。
お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります