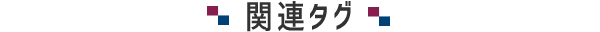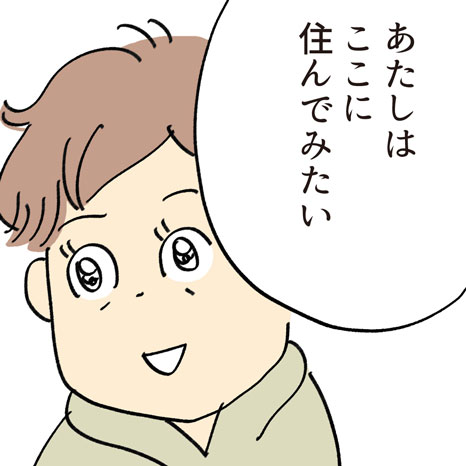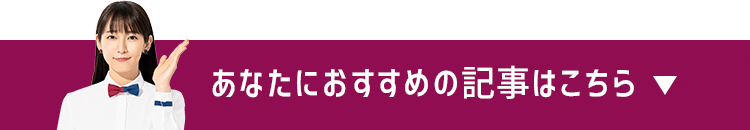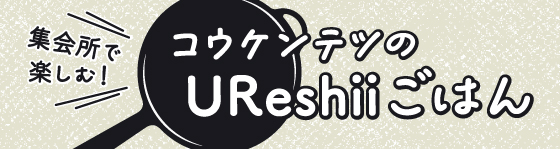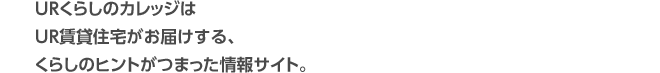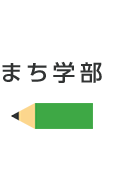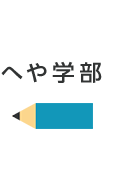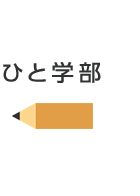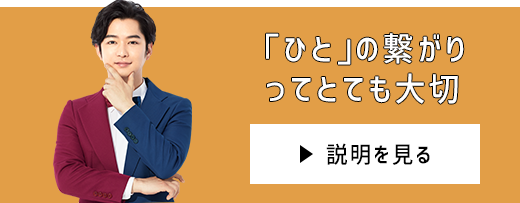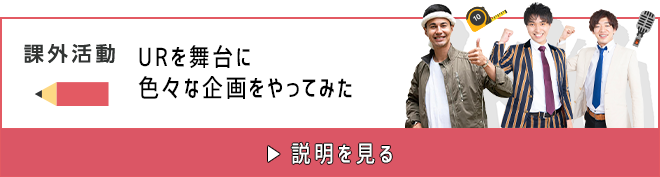住みたいへやの選び方
老後に賃貸住宅に住むメリット・デメリット、物件選びのポイント

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります
住居費は生活費の中で大きい支出の一つです。「老後に備えて、マイホームを購入するか、賃貸にするか…」と、住まい選びに悩む方も多いのではないでしょうか。実際には賃貸と持ち家、一戸建てとマンション、自宅と老人ホームなどさまざまな選択肢があります。その中でも、今回は賃貸住宅に焦点を当て、メリットやデメリットを紹介します。定年後ではなく余裕のあるうちから、しっかりしたライフプランを立てておきましょう。
老後に賃貸住宅で暮らすメリット・デメリット

賃貸住宅は資産にならない半面、ライフステージに合わせて、柔軟に住み替えできる利点があります。まずはデメリットから解説します。
●デメリット
- <家賃を払い続ける必要がある>
- 賃貸住宅に住み続ける限り、毎月、家賃や管理費などの支払いが必要です。必要な生活資金として、年金以外にも安定した収入源が必要になることがあります。住宅ローンを完済すると自分の資産になる持ち家と異なり、お金を払い続けても資産にはならないため、あらかじめコストを計算して貯蓄をしておくことが大切です。
- <シニア世代になるほど借りられる物件が限られる>
- 持ち家はシニア世代になっても住み続けることができますが、賃貸住宅に入居する際に、シニアの方は入居審査で断られることがあります。さらに一人暮らしの場合は、認知症の発症や孤立死の不安があると思われることが多く、特に孤立死は不動産価値が下がると考えられているようです。
- <自由にリフォームすることが難しい>
- 持ち家の場合は自己負担で自由自在にリフォームすることができます。そのため身体機能の低下に応じたバリアフリー化も可能です。しかし賃貸住宅は原則として原状回復義務があるため、ほとんどの物件で自分の都合で自由にリフォームすることができません。いくら老後にバリアフリー化を希望しても、現状では工事を伴うものはなかなか受け入れてもらえないでしょう。
●メリット
- <住み替えをしやすい>
- 持ち家と違いライフスタイルの変化に合わせて気軽に住み替え・引っ越しができるのが大きな魅力です。例えば、子供の独立(一人暮らし)、収入の減少、定年退職に伴う転居、高齢者向け施設への入居など、ライフステージによってさまざまな状況になる可能性がありますが、その都度、部屋数などを変えながら状況に合わせて最適な住まいの選択を行うことができます。
- <固定資産税などがかからない>
- 持ち家の場合、毎年、固定資産税と都市計画税を支払う義務がありますが、賃貸住宅の場合は不要です。煩雑な税金の手続きも必要ありません。
- <建物の修繕費用の負担がかかりにくい>
- 設備の故障による修理費や経年劣化による交換費用、建物の老朽化による改修は、持ち家の場合はすべて自己負担になります。しかし賃貸住宅の場合、入居時の設備が通常の使用方法で故障したときにかかる費用は、オーナーの負担になります。このため、故障したときも管理会社やオーナーへ連絡するだけで済むので手間や費用面での負担は多くないでしょう。
- <住宅ローンを組まずに済む>
- 住宅ローンを組んだ場合、収入の減少による返済困難などのローンリスクを、将来にわたって抱えなければなりません。世帯主に万が一のことが起こるリスクもあります。賃貸住宅であれば、家計が厳しくなったとき、家賃の安い物件へ引っ越しすることも可能です。また住宅ローンを払った場合でも、持ち家を売却して賃貸住宅に住み替えをすると、売却して得たお金をほかの資産として残すことができます。
- <相続のトラブルが起こりにくい>
- 持ち家や土地の所有者が亡くなると、配偶者や子供などに不動産を相続します。資産価値が高いとき、相続人に対して多額の相続税が発生する可能性があります。また、相続人が複数いる場合には、遺産の分配が問題となり親族間のトラブルに発展する場合もあります。賃貸住宅の場合は相続の対象にならず、相続税も発生しないため、物件の名義変更や再契約の手続きを行えば同じ家に住み続けることができます。
老後に住む賃貸住宅を選ぶポイント

ひと口に賃貸住宅といっても、さまざまな選択肢があります。老後に住む賃貸住宅のポイントをチェックしていきましょう。
●バリアフリー化されている
賃貸住宅でバリアフリーのリフォーム工事を行うことは難しいため、すでにバリアフリー化されているかどうかが大切です。例えば、段差がない、手すりが多い、車いすの通り道がある、などが挙げられます。また、シニアの方にとって使いやすい間取りであることもポイントです。将来を想定して、トイレが寝室に近い、廊下が広く車いすで通りやすいなどのポイントに注意して間取りも確認しましょう。
●立地条件が良い
日々の暮らしに負担が生じにくい便利な環境が良いでしょう。例えば、最寄り駅が近い、周囲に坂道が少ない、かかりつけの病院が近くにあるなど、生活する上で必要な施設が近くにあり、体に負担が少ない環境が望ましいです。
●シニアの方の入居実績がある
オーナーによっては、シニアの方の入居を快く思わない方もいるため、あらかじめシニアの方の入居実績があるかどうかを確認すると良いでしょう。入居実績があれば、シニアの方の住みやすい部屋かどうかの判断材料にもなります。
●家賃が比較的リーズナブル
老後資金が潤沢でない場合は、初期費用やランニングコストを含めてリーズナブルな費用の賃貸住宅を選ぶことをおすすめします。年金生活を送る中で、住居費は大きな出費となるため、生活費も加えてシミュレーションしながら、貯蓄と収入・支出のバランスを取るようにしましょう。
●シニアの方のコミュニティが近くにある
シニア世代になると人とかかわる機会が少なくなり、引きこもって孤立してしまうことがあります。夫婦や家族とのかかわりだけでなく、積極的に地域のコミュニティカフェや将棋・碁会所、図書館、居酒屋などに出かけてみましょう。他者と交流ができて、自宅以外の居場所となるコミュニティがあると精神的にも身体的にも、健康的に過ごしやすくなります。
●健康管理のための施設がそろっている
身体機能の低下を防ぐために、近くの公園でのウオーキングや、ジムに通ってのエクササイズも良いでしょう。さらに健康管理をしてくれる、かかりつけ医とのかかわりも大切になってきます。コミュニティと同様に、そのための施設が近くにそろっているか、確認しておきましょう。
老後の住まいにふさわしい「UR賃貸住宅」の特徴

高齢者向けの賃貸住宅なら、UR賃貸住宅がおすすめです。独立行政法人都市再生機構が運営する賃貸住宅で、豊富な物件から好みに合った住まいを自由に選ぶことができます。
●初期費用を抑えやすい
URは礼金・仲介手数料が不要です。さらに更新料も不要。契約時に必要なお金は、敷金(月額家賃の2カ月分)と、入居日から月末までの日割り家賃、日割り共益費のみ。そのため新規契約時の初期費用を大幅に抑えることが可能です。契約更新時の更新料の負担もなく、自動更新で手続きが不要なため、安心して住み続けることができます。家賃以外の費用を節約できるのがメリットです。
●保証人が不要
シニアの方の場合、保証人の依頼が難しい傾向にあります。保証人となる兄弟姉妹や友人もシニア世代となるケースが多く、支払い能力がないと見なされることがあるためです。その点でもURは安心です。保証人も不要で家賃保証会社に支払う保証料もかからないため、利用しやすくなっています。
●見守りサービスがある
URではシニアの方のために、有料の見守りサービスを実施しています。住まいの壁や天井にセンサーを設置。住民の動きが確認できないときは、コールセンターから住民本人に電話確認し、必要に応じて緊急連絡先へ連絡してくれるので安心です。
●高齢者向け賃貸住宅を供給している
シニアの方が利用しやすいよう、設備やシステムを改良した高齢者向け賃貸住宅を多数供給しています。「高齢者向け優良賃貸住宅」、「高齢者向け特別設備改善住宅」、「健康寿命サポート住宅」、「シルバー住宅」、「URシニア賃貸住宅(ボナージュ)」など、ライフスタイルに合わせて、さまざまな物件が準備されています。それぞれ設備の概要と申し込み条件などが異なります。
●住環境が良い
URでは建物同士がゆったりした間隔で建てられ、敷地内に緑豊かな公園や広場が設けられた物件が多いのも特長です。敷地内には木々や草花が植えられ、ベンチなども設置されるなど、自然を感じやすい環境。シニアの方でも安心して散歩を楽しむことができます。長い時間をかけて地域に根ざしてきたので、近くで必要なものがそろいやすい買い物環境も整っている場合が多くなっています。
●お得な家賃プランがある
URではシニアの方が対象となる、お得な家賃プランも用意しています。また公的年金で生活している方には、家賃の前払い制度などがあります。
- <近居割>
- 募集家賃から5年間、5%減額されます。対象となるのは同じUR内、もしくは半径2km以内の別々のURで、親世帯・子世帯の二世帯が近居する場合で、新たに契約した世帯の家賃が減額されます。また、二世帯同時に契約する場合は、両世帯とも減額されます。
- <フリーレント>
- URが定める期間中に申し込めば、その間の家賃が無料となるフリーレント物件があります。1カ月フリーレントと2カ月フリーレントの物件があり、例えば、1カ月フリーレントで入居開始可能日が2月11日なら3月11日以降分から家賃の支払いが始まり、2カ月フリーレントなら家賃の支払いが始まるのは4月11日以降分からとなります。
URのフリーレントと「4つのナシ」を組み合わせれば、入居時にかかる初期費用は共益費と敷金のみとなり、初期費用をさらに大幅に抑えることが可能です。ただし、契約期間の途中で解約した場合、フリーレント期間中の家賃の支払いが発生することがあります。フリーレント期間が1カ月の場合は入居開始可能日から1年以上、フリーレント期間が2カ月の場合は入居開始可能日から2年以上、継続して入居することが条件となります。
賃貸住宅でも老後は安心。自分の状況に合わせて最適なライフプランを

「マイホームを購入するか、もうしばらく賃貸住宅でいるか、老後も賃貸住宅に住み続けるか?」住んでいる場所や年収など、自分の置かれた状況によって判断は異なりますが、住居費にまつわる決断に悩みは尽きません。
今回は賃貸住宅に焦点を当てましたが、メリット・デメリットをそれぞれ理解しつつ、さまざまな選択肢を比較・検討・試算した上で、老後のライフプランを立てていくのが良いでしょう。賃貸住宅に住むことも検討することで、選択肢もこれまでより幅広くなるのではないでしょうか。
老後に賃貸住宅を選ぶなら、UR賃貸住宅がおすすめです。一般的にいわれるような入居拒否や保証人の問題もなく、住み替え時の初期費用も抑えることができます。さらに「高齢者向け優良賃貸住宅」など、シニア世代専用の賃貸住宅も充実しています。
老後にどんな暮らしをしたいか、良い機会なのでしっかり考えてみてはいかがでしょうか?
監修/大久保 恭子

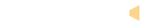
賃貸住宅も考慮に入れて、老後のライフプランを考えよう
- ・老後に賃貸住宅に住むデメリットは家賃を払い続ける必要があり、シニア世代になるほど借りられる物件が限られて、自由にリフォームすることが難しいこと
- ・メリットは住み替えをしやすく、住宅ローンを負わなくて良いこと。固定資産税などがかからず、相続のトラブルが起こりにくいこと
- ・UR賃貸住宅は高齢者向けの物件やサービスも充実していて、初期費用も抑えられるのでおすすめ

くらしのカレッジ編集部は、「くらし」に関するさまざまなヒントをお届けすることを目的に、インテリア、リノベーション、DIY、子育て、イベント情報など、生活を豊かにするアイデアや日常的に楽しめるコンテンツをご紹介しています。
お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります