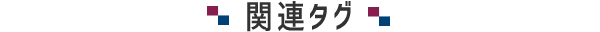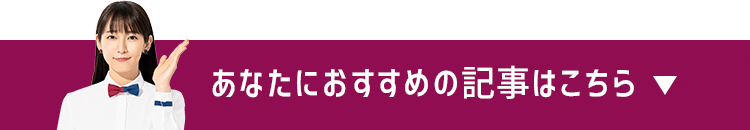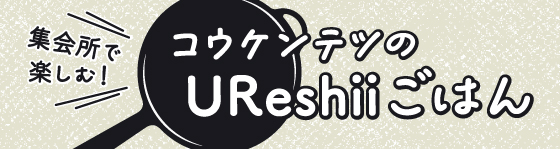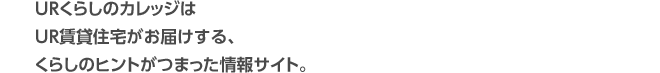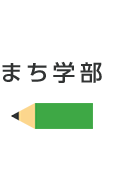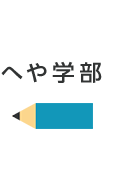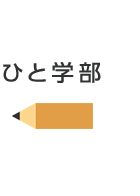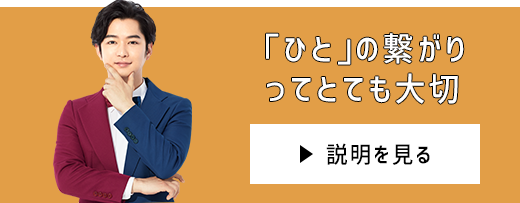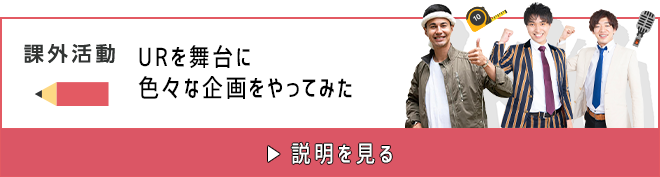これからのくらしを考える ひと×団地
新事業メッセージ「ゆるやかに、くらしつながる。」が意味するURの魅力とは?東京大学 大学院の大月教授に教えてもらいました!

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります
2025年7月、団地誕生から70年を迎えるに当たり、UR賃貸住宅では、新しい事業メッセージ「ゆるやかに、くらしつながる。」を発表しました。このメッセージは専門家の目にどのように映っているのでしょうか。
建築計画や住宅地計画が専門である東京大学 大学院工学系研究科建築学専攻の大月敏雄教授にお話をうかがいました。
新事業メッセージに込められた思い
UR賃貸住宅の前身となる日本住宅公団は1955年(昭和30年)に設立されました。その時代から今日に至るまで、UR賃貸住宅は時代ごとの社会課題に向き合いながら人々が安心して暮らせる住まいのあり方を提案してきました。そんなUR賃貸住宅が新たに掲げた事業メッセージが「ゆるやかに、くらしつながる。」。
この事業メッセージについて、長年、集合住宅や居住環境について研究をしている大月教授はどのように感じたのでしょうか?

一見べたに見えるのですが、よく練られたフレーズだと思いました。
まず注目するのは「くらし」という言葉。住宅の供給は、物件を提供するだけの時代から、そこに住むことで得られるプラスアルファの価値を求められる時代へとシフトしています。例えば、福祉にアクセスできる、特定のサービスが受けられる、コミュニティによって暮らしそのものの価値を高めることができるといったようなことです。そのプラスアルファが、この「くらし」に入っていると思います。
そうした文脈の中で、「つながる」が持つ意味も今の社会だからこそ重要です。“個”の時代が進み、一人暮らしが増え、多様な人が団地に住んでいる今、それぞれの悩みを個別で解決するには、限界があります。
大小さまざまな悩みを抱える人たちに「つながることもできるよ」というメッセージを出しているのが、これまでと違ったアピールじゃないかと思います。


そして大きな意味を持つのが「ゆるやかに」という言葉。我々の暮らしって、いつ子どもが生まれるか、いつパートナーが認知症になるか、分からないじゃないですか。明日かもしれないし、5年後かもしれない。
そういった予測できない人生の時間軸を受け止める余白が「ゆるやかに」にあると思うんです。
「ゆるやかに」という言葉は、人と人の間合いにも通じます。例えば、気分が晴れていたらあいさつも自然にできる。でも気分が沈んでいたら、そっとしておいてほしいときもあって、気持ちってコロコロ変わるでしょう。
若いとき、元気なときは「コミュニティはあまり関係ない」と思うかもしれません。ただ、心細いときに「誰かに手助けしてほしい」と思った経験はあるのではないでしょうか?
そのような、変化する状況に対応できる余白とコミュニティとの関わり方を自分で選べるということが、この言葉に表現されていると感じています。
団地の空間そのものが持つ力
レトロな存在と思われがちな団地ですが、実は今、新たな注目を集めていると大月教授は語ります。

最近、「第三次団地ブーム」が来てると感じているんです。第一次は昭和30年代。「団地族」(※)という言葉が出てきたころで、「団地に住むって格好良い!」という空気がありました。第二次は2000年ごろで、団地写真集の発売など、団地を愛でる文化が広がっていました。
今はどうかというと、NHKドラマ『団地のふたり』、『しあわせは食べて寝て待て』、映画『雨を告げる漂流団地』のように、団地を舞台にした作品が注目されているんです。団地が単なる懐かしい場所ではなく、若い世代にとっても「今だからこそ暮らしたい」場所になりつつあるはずです。
※高度経済成長期に、団地に住みモダンな生活を送っていた人のこと

 )
)なぜ今、団地を魅力的に感じる人が増えているのでしょうか? 住棟や敷地内の構造に秘密があるようです。

団地には「人と人がつながるきっかけ」が、ちゃんと織り込まれているんです。
例えば、昔ながらの5階建ての団地の階段室。ここで住民同士が日常的にすれ違うと、自然とあいさつを交わすようになります。これは人間の体に染み込んだ行動文化なんです。
また、住棟下にあるポストをのぞいたり、掲示板を見たり、外を歩いている人とベランダから視線が交わったりと、自然と人とすれ違い、あいさつができる環境になっています。


もう一つ面白いなと思ったのは、団地に住んでいる人はラフな格好で外のごみ捨て場に行くということです。団地の敷地が、自分の家の延長のような感覚なのではないでしょうか。そのような気安さを団地の空間自体がつくっているんです。
こんな風な「心のハードルが低い空間」が、まさにUR団地の強みだと思っています。「ラフで良いよ」と言ってくれているかのような団地全体の雰囲気が、家の外にもあることで、つながりやすくなっています。

安心感をはぐくむゆるやかなつながり
人と人とが自然とつながる仕掛けが備わっているURの団地。あいさつや会話を通してつながることが心にゆとりを生むのだそうです。

今の団地は、若者、子育て中の方、シニア世代、外国人、障害がある方など、多様な人たちが混ざり合い、それぞれ悩みや課題を抱えて暮らしています。同じ団地に住んでるからといって仲良くしなければならないわけじゃないですが、「この人だったらちょっと話せるかも」と思えるような存在が近くにいるというだけで、暮らしの安心度は大きく向上します。


僕が行った団地では、ベンチでたくさんのおじいちゃん、おばあちゃんがおしゃべりをしていました。あるおばあちゃんが隣の人に「デーって何?」と聞いていて、おそらく「デイサービス」のことですが、気になっていても人に話せなかったようなんですね。
そんな風にその場の空気が背中を押してくれて、自然に質問できたり、「じゃあ一緒に行ってみようか」なんて会話が生まれたりする。そういうことが、介護予防や福祉とのつながりをつくるきっかけにもなるし、抱えていた悩みがふっと軽くなることもあるんです。実はそれって、とても大切なことなんですよね。
みんなが会話をするのは、最初から課題を解決するためじゃなくて、ただ「誰かにちょっと聞いてほしい」という気持ちを解放したいからです。だからこそ、そんな「心のハードルが低い空間」があるURの団地って、今の時代にすごく合っていて魅力的なんだと思います。

心地よい距離感で人と出会い、自分らしい生活を送ることができるUR賃貸住宅。今後もゆるやかなつながりをはぐくむ住環境を提供し続けることを目指しています。

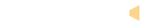
ゆるやかにつながることができるUR賃貸住宅で、暮らしの安心と豊かさをはぐくむことができる
- ・団地誕生70年を機に、UR賃貸住宅が新・事業メッセージ「ゆるやかに、くらしつながる。」を発表
- ・階段室やベランダ、ベンチなど、UR賃貸住宅の団地には「人と人がつながるきっかけ」が、織り込まれている。会話やあいさつが生まれやすくなる「心のハードルが低い空間」が、UR賃貸住宅の魅力
- ・団地内に顔見知りや話せる人がいると暮らしの安心度は大きく向上する
大月 敏雄さん
東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 教授。
東京大学 高齢社会総合研究機構 副機構長。ハウジングアンドコミュニティ財団理事。博士(工学)、一級建築士。
専門は建築計画、住宅地計画、ハウジング。
著書に『町を住みこなす―超高齢社会の居場所づくり』(岩波新書)、『市民がまちを育む―現場に学ぶ「住まいまちづくり」』(建築資料研究社)などがある。
2019年、日本建築学会賞(論文)受賞。


くらしのカレッジ編集部は、「くらし」に関するさまざまなヒントをお届けすることを目的に、インテリア、リノベーション、DIY、子育て、イベント情報など、生活を豊かにするアイデアや日常的に楽しめるコンテンツをご紹介しています。
お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります