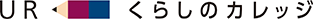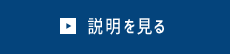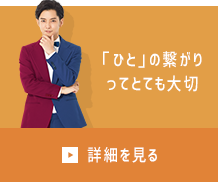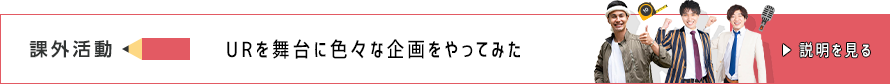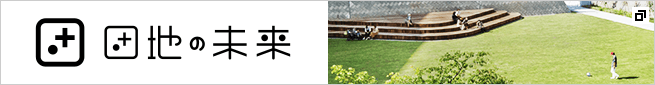住みたいへやの選び方
賃貸借契約の初期費用の相場は?安く抑えるコツと払えない場合の対処法

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります
賃貸住宅を借りるときは、家賃ばかりに注目してしまいますが、意外と忘れられているのが初期費用。「物件を借りるには家賃の2~6カ月分が必要」といわれますが、敷金、礼金以外にも、引っ越し費用や家具、家電の購入費用なども必要です。これらを合わせると想定外の出費になることもあるため、事前に知識を付けておくことが大切です。今回は、初期費用の基礎知識から相場、初期費用を抑える方法、支払えない場合の対処法を紹介します。
賃貸借契約の初期費用を解説!費用の内訳とよくある疑問

賃貸住宅を借りる際にかかる初期費用には、どのようなものがあるでしょうか。まずは、初期費用の基礎知識を学びましょう。
●初期費用とは?
初期費用とは、賃貸住宅の入居時に支払いが必要となる費用で、敷金、礼金、前家賃、仲介手数料、保証料、火災保険料などが含まれます。初期費用とは別に、引っ越し費用なども発生するため、入居時は出費が多くなりがちです。初期費用を支払うタイミングは、賃貸借契約の締結後になります。賃貸借契約は、借主が気に入った物件に入居申し込みを行って、大家さんや不動産会社による入居審査の後の締結となり、この際に初期費用を支払います。なお、重要事項説明とは不動産会社などの宅地建物取引業者が、当事者に対して契約上重要な事項を説明する制度です。
●初期費用の内訳
- ・敷金
- 敷金は、退去時の原状回復費用や家賃滞納をした際に備え、大家さんに預けておくお金です。契約終了後、退去後にそれらが引かれて戻ってきます。一般的には家賃の1~2カ月分程度ですが、敷金ゼロ物件も最近は増えてきました。その場合、退去時にクリーニング代が必要になることがありますので注意しましょう。関西では、関東とは商習慣が違い保証金と呼ぶケースがあります。
- ・礼金
- 礼金は、賃貸住宅を貸してくれる大家さんに、お礼として支払う費用です。敷金は保証金的な意味合いがあり、退去後に戻ってくるケースがありますが、礼金は退去時に戻ってきません。家賃の0~2カ月分程度が多く、近年は礼金なしの物件の割合が増えています。
- ・前家賃
- 一般的に、家賃は当月分を当月末でなく、前月末に支払います。例えば契約が2月で3月から入居する場合、3月の家賃を事前に支払うことになります。月の途中から入居する場合には、契約時に当月分の日割り家賃が発生します。
- ・日割り家賃
- 入居日から月末までの月の家賃を、日割り計算した費用です。月の途中から入居する場合に発生するため、事前に計算して支払い金額を把握しておくことが重要です。
- ・仲介手数料
- 物件の案内や、契約手続きを行った不動産会社に支払う費用です。家賃の0.5~1カ月分+消費税が目安となり、法律により上限は「家賃の1カ月分」と定められています。
- ・火災保険料
- 火災や水漏れトラブルなどに備えて加入する保険です。損害保険会社に支払う費用となります。賃貸借契約では、加入する義務があります。一人暮らしで1.5万円、家族で暮らす場合は2万円前後が一般的な相場です。
- ・保証料
- 家賃保証会社を利用する場合に支払う費用。家賃の0.5~1カ月分が目安です。この費用は、家賃が支払えなくなったときの備えとして徴収され、基本的には返還されないため、必要に応じて事前に確認しておくことが重要です。連帯保証人がいれば不要なケースもありますが、保証会社への加入が必要な物件が増えています。
- ・管理費・共益費
- 賃貸マンションなどの集合住宅の共用部分を管理・維持するためにかかる費用です。家賃の5~10%が相場になり、清掃費用、設備にかかる光熱費、保守点検費用、管理人の人件費などに使われています。ただし、不動産会社によって、家賃に含まれていたり、別途徴収されたりと、支払い方法が異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
- ・そのほか(鍵交換費用・消毒料など)
- 上記のお金のほかに、鍵交換費用や消毒料といった名目で設定された費用を、契約時に請求されることがあります。これらの費用は、契約時に発生することが一般的で、特に鍵交換はセキュリティーの観点から重要です。また、消毒料は新たな入居者のために物件を清潔に保つ目的で請求されることがあります。初期費用の項目は、契約する物件や不動産会社で異なりますので、契約する前にしっかり確認してください。
●初期費用に関するよくある疑問
- ・敷引き(しきびき)とは?
- 主に西日本に見られる賃貸借契約での商慣習で、「保証金」とセットで使われる場合が多い傾向にあります。名目としては物件の修繕費用で、退去時に大家さんに預けた保証金から一定額の金額が差し引かれて、返還される制度になります。なお差し引かれる金額は事前に決まっています。例えば「保証金2カ月、敷引き1カ月」の場合、退去時に家賃1カ月分が引かれた、1カ月分の保証金が返還されます。保証金と敷引きが同額の場合は、退去時の返還はありません。
- ・敷金はどれくらい返還される?
- 預けた敷金のうち、借主負担となる原状回復費用を引かれた金額が返還されます。借主による故意や過失などが原因のものは、借主の負担となってしまうので注意しましょう。国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、借主の原状回復義務の基本的な考え方は、「賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、そのほか通常の使用を超えるような使用による損耗などを復旧すること」と定義されています。そのため、壁の下地ボード張り替えが必要になるようなねじ穴、たばこのやにによるひどい汚れ、結露の放置によるカビなどは、借主負担となります。また、原状回復費用に加え、退去時のクリーニング費用を引かれる場合もあります。この場合、特約として賃貸借契約に盛り込まれていることが一般的です。賃貸借契約時には、特約までしっかり目を通しましょう。
賃貸借契約で知っておくべき初期費用の相場とは?具体的に計算した目安を解説

初期費用について、実際にはどのくらいの費用を目安に考えておけば良いのでしょうか? 一人暮らしの場合、家族で暮らす場合の相場を解説していきます。初期費用を把握し、予算に合わせた物件探しを行うことで、経済的な負担を軽減できるでしょう。
●家賃7万円の場合(一人暮らしの想定)
敷金、礼金がそれぞれ家賃の1カ月分の物件に入居する場合、初期費用の相場は37.2万円になります。
- • 敷金7万円(家賃1カ月分)
- • 礼金7万円(家賃1カ月分)
- • 前家賃7万円
- • 日割り家賃3.5万円(半月分で計算)
- • 仲介手数料7.7万円
- • 火災保険料1.5万円
- • 保証料3.5万円
初期費用の37.2万円は、家賃のおよそ5倍。物件によって多少変動することを考慮に入れておいた方が良いでしょう。また、この初期費用には物件によって家賃の中に管理費(共益費)が含まれていない場合もあり、そのほかにも、引っ越し費用や、新生活の場合には、家具や家電の購入費用なども発生するため、事前にしっかり計算しておきましょう。
●家賃12万円の場合(家族で暮らす想定)
初期費用の相場は63.2万円になります。
- • 敷金12万円(家賃1カ月分)
- • 礼金12万円(家賃1カ月分)
- • 前家賃12万円
- • 日割り家賃6万円(半月分で計算)
- • 仲介手数料13.2万円
- • 火災保険料2万円
- • 保証料6万円
家族で暮らす場合には、一人暮らしの場合以上に、引っ越し費用や家具、家電の購入費用がかかる傾向にあるため、引っ越し資金は余裕を持って準備をしましょう。
賃貸借契約で初期費用を抑えるための効果的な方法

思っているよりも高くなりがちな初期費用ですが、ポイントを押さえれば、低く抑えることもできます。それではどのような方法があるか、ここで紹介します。
●不動産会社の仲介手数料が安い物件を選ぶ
賃貸借契約を結ぶ際には、仲介手数料が発生することが一般的ですが、これを少しでも軽減するための方法があります。例えば、不動産会社に相談する前に、ネットを通じて、仲介手数料の金額を確認するほか、自社所有物件の有無を確認しましょう。自社所有物件がある場合には、貸主との直接契約になるので仲介手数料が不要になる場合があります。また、地域によっては不動産会社が競合しているため、特別なプロモーションやサービスを実施している場合があります。
入居者が大家さんと直接契約可能な会社の場合、仲介手数料が発生しないケースもしばしばあるため、事前に確認しておくことが大切です。加えて、最近では、仲介手数料をゼロにしたり、0.5カ月分など低額に抑えたりしている会社も増えているため、各社の情報を集めて交渉に生かすと良いでしょう。
こうした仲介手数料が少ない、もしくはかからない物件を探してみてはいかがでしょうか。
●不動産会社に希望を伝える
不動産会社に、あらかじめ初期費用に関する希望を伝えることで、希望に合う物件を紹介してもらえる場合があります。特に敷金、礼金は、条件として伝えやすく、低価格またはゼロの物件などを紹介してもらえることもあります。あらかじめ予算を伝えることで、ミスマッチがなくなり、お互いにメリットがあります。
●フリーレント物件、敷金・礼金ゼロの物件を探す
フリーレント物件や敷金・礼金ゼロ物件は、賃貸借契約をする際の初期費用を大幅に軽減する有効な手段です。フリーレントとは、入居後の家賃が一定期間無料になるシステムです。通常は1カ月分の家賃が無料となるケースが多いですが、条件として一定期間入居しないとペナルティーがあるのが一般的です。フリーレントは家賃が一定期間無料であり、礼金や敷金がゼロというわけではありません。そのため、契約内容をしっかり確認しておくことが重要です。また敷金、礼金が不要な物件、いわゆるゼロゼロ物件も最近増えています。フリーレント物件やゼロゼロ物件は、入居時にかかる費用を抑えることができるため、探してみることをおすすめします。
●不動産会社の繁忙期を避け、閑散期を狙う
不動産会社の繁忙期は需要が増えるため、敷金や礼金などの初期費用が割引されにくい傾向にあります。繁忙期は1~3月と、9~10月。それぞれ入学や入社、転勤などが増えやすい時期です。選べる物件は増えますが、割引は期待できません。また閑散期は、敷金や礼金などの初期費用が繁忙期に比べ割引されやすい傾向にあります。閑散期は6~8月。大家さんはなるべく空室を減らしたいため、繁忙期に比べ減額することがあります。さらに、引っ越し業者も繁忙期ではないため、引っ越し料金の見積もりもリーズナブルになりやすく、家賃、引っ越しともにトータルで費用を抑えることができます。
●荷物を減らす
すぐに始められることとして、荷物を減らすことも有効です。より専有面積の小さい家に引っ越しして、家賃などの初期費用を減らすことができるだけでなく、運ぶ荷物量が少なくなると、引っ越し料金も安く抑えることができます。引っ越しを検討しているのであれば、まずは服、家具、本など不要なものを捨てて、生活をコンパクトにするところから始めてみると良いでしょう。
●UR賃貸住宅を検討する
UR賃貸住宅なら、礼金、仲介手数料、また保証人が必要ないため保証料もかかりません。そのため初期費用だけで、一般的な相場と比較して、家賃2~3カ月分を節約することができます。
<UR賃貸住宅で家族と暮らす場合(家賃12万円、共益費4000円の想定)のシミュレーション>
- • 敷金24万円(家賃2カ月分)
- • 礼金0円
- • 前家賃0円
- • 日割り家賃6万円(半月分で計算)
- • 日割り共益費2000円(半月分で計算)
- • 仲介手数料0円
- • 火災保険料任意
- • 保証料0円
初期費用は30.2万円、家賃1カ月分の3倍以下。一般的な賃貸住宅の場合には、63.2万円のため、30万円以上の初期費用が抑えられます。さらに、初期費用だけでなく、2年ごとの更新料もURの場合は必要ありません。これにより、契約後、仮に2年住めば更新料分のお金が浮くと考えられるため、ぜひ検討してみると良いでしょう。
賃貸住宅の初期費用が払えない場合の対処法

初期費用はまとまった現金が必要になります。全額支払うのが難しい場合は、一括で支払う以外にもいくつか方法があるので、検討してみると良いでしょう。
●分割払いが可能な不動産会社やクレジットカードを利用する
不動産会社によっては、分割払いに応じてもらえる場合があります。支払い方法は、クレジットカード払いと現金払いの2種類があり、クレジットカード払いの方が多い傾向にあります。またクレジットカードの一括払いしかできない場合でも、支払い後にカード会社に連絡して分割払いにする方法もあります。
ただし、クレジットカードの場合、支払い回数が増えるにつれて、金利・手数料がかかり、総額で支払う費用が増えるため注意して利用する必要があります。収入とのバランスを考えて、計画的に行うようにしましょう。
●ローンを利用する
融資目的が限定されていない銀行のフリーローン(多目的ローン)を、賃貸住宅の初期費用の支払いに利用することが可能です。クレジットカードのカードローンよりも低金利で借りることができますが、申請から融資までに時間がかかることが多く、金利がかかり総額も増えるので、注意して利用するようにしましょう。借り入れを行う際には書類や審査基準を事前に確認し、スムーズな手続きが行えるようしっかりと準備を整えておくことが重要です。自分の返済能力を考慮し、先々を見据えた無理のない計画を立てましょう。
●自治体の助成金を調べる
引っ越し時の初期費用の一部に助成金が出る自治体があります。助成金を受けられる条件がそれぞれ定められているので、引っ越し先の自治体の助成金を確認しておくと良いでしょう。助成金対象となりやすい条件は、例えば、子育て世帯、新婚世帯、ひとり親世帯、高齢者世帯、障害者世帯があります。自治体によって対応が異なりますが、家賃補助だけでなく、引っ越し費用まで助成してもらえるので、該当する場合はまず自分で調べてみることをおすすめします。
賃貸借契約で避けられない初期費用。引っ越し費用や家具・家電購入費も忘れずに

「いざ賃貸借契約を結ぶときになって、初めて初期費用の額を知る」ということは、避けたいところ。物件を探す段階で、初期費用も考慮に入れて進めるようにしましょう。家賃の2~6倍を目安として、費用をあらかじめ把握しておくようにしましょう。事前に初期費用のことを知っていれば、不動産会社とのやり取りもスムーズに進めることができて、こちらの要望に合った物件に出会える確率も高くなります。もし、初期費用が高額で困った場合でも大丈夫。分割などで賢くやりくりする方法もあります。引っ越す必要性が高い場合は対処法を検討すると良いでしょう。今回紹介したUR賃貸住宅のように、初期費用などを抑えることができる賃貸住宅もあります。事前にしっかりと計画を立て、納得のいく住まい選びをしてくださいね。
監修/加藤 哲哉

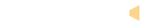
初期費用は抑えられる!物件探しのときから計画性を持って進めよう
- ・初期費用の相場は家賃の2~6倍が目安。物件によって異なるので注意が必要
- ・初期費用を抑えるためには、初期費用がお得な物件を探したり、不動産会社や大家さんと相談したりすることが大切
- ・UR賃貸住宅なら一般的な相場と比較して、家賃2~3カ月分の初期費用を抑えることができる
- ・さらにURは更新料も不要。2年以上住む可能性が高い場合は特におすすめ
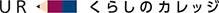
くらしのカレッジ編集部は、「くらし」に関するさまざまなヒントをお届けすることを目的に、インテリア、リノベーション、DIY、子育て、イベント情報など、生活を豊かにするアイデアや日常的に楽しめるコンテンツをご紹介しています。
お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります